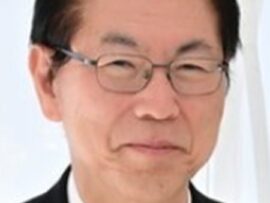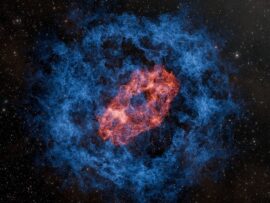日本の停滞感、閉塞感。その根底には、私たちの社会を深く支配する「暗黙のルール」が存在するかもしれません。社会学者・小熊英二氏の著書『日本社会のしくみ』を参考に、日本社会の硬直化の要因を探り、現代社会における「地元型」生活者の影響力について紐解いていきます。
現代日本における「地元型」の割合とは?
「地元型」とは、生まれ育った地域に根ざし、その地域社会の価値観や人間関係を重視する生活スタイルを指します。では、現代社会において、この「地元型」の人々はどの程度の割合を占めているのでしょうか?
正確な数値を算出するのは困難ですが、国勢調査や各種統計データから推計してみましょう。2015年の国勢調査によると、出生時から同じ居住地に住んでいる人は全体の13.8%、20年以上同じ居住地に住んでいる人は31.4%となっています。
 20年以上同じ居住地に住んでいる人の割合
20年以上同じ居住地に住んでいる人の割合
しかし、後者には都市部の郊外に長年住む大企業勤務者なども含まれます。そこで、三大都市圏(東京、名古屋、大阪)を除外した20年以上同一居住地に住む人と、出生時から同一居住地に住む人を合計すると、全体の27.8%となります。
この数値にはUターン者は含まれていません。そこで、国土交通省の2015年の国民意識調査を参照すると、三大都市圏以外の地域では「定住者」が23.4%、「Uターン者」が54.5%という結果が出ています。これらのデータから、「地元型」と分類できる人々は全国で約4590万人、総人口の36.1%と推計されます。
三大都市圏以外では「地元型」が圧倒的多数
注目すべきは、三大都市圏以外の地域では「定住者」と「Uターン者」の合計が77.9%に達することです。つまり、地方においては「地元型」の生活者が圧倒的多数派を占めているのです。
この状況は、選挙区の分布とも相まって、国会議員に届く声にも影響を与えていると考えられます。地方の声が政治に反映されやすい構造になっていると言えるでしょう。 食文化研究家の佐藤香織氏(仮名)は、「地方の食文化は、地元の食材や伝統的な調理法を重んじる傾向が強く、それが地域社会の繋がりを強固にしている」と指摘しています。
過去と比較して「地元型」は減少傾向?
過去における「地元型」の比率は不明ですが、政府の人口問題研究所の調査によると、1966年には調査対象の男女の9割以上が同県人と結婚していたというデータがあります。その後、経済成長に伴う人口移動により、県内結婚の割合は減少しました。

これらのデータから、1960年代以前の日本では、多くの人々が狭い地域範囲で結婚し、「地元型」の生活を送っていたと推測されます。それと比較すると、現在の36.1%という数字は、大幅な減少と言えるでしょう。
現代社会における「地元型」の影響力
「地元型」の生活者は、地域社会への愛着が強く、地域の伝統や文化を大切にします。それは、地域経済の活性化や地域コミュニティの維持に貢献する一方で、新しい価値観や変化への抵抗を生み出す可能性も秘めています。
小熊氏は、この「地元型」の思考様式が、日本社会の硬直化、変化への抵抗の一因となっている可能性を指摘しています。グローバル化が加速する現代において、地域社会の重要性は変わりませんが、多様な価値観を受け入れ、変化に対応していく柔軟性も求められています。
日本社会が停滞から脱却し、新たな未来を切り開くためには、「地元型」の価値観と、変化への対応をバランスよく両立させていく必要があると言えるでしょう。