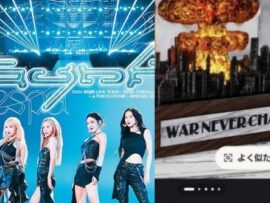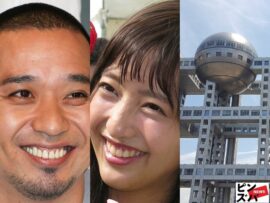日本の建国神話に欠かせない神武天皇。そのお墓とされる神武天皇陵は、奈良県橿原市に荘厳な姿を見せています。しかし、その歴史を紐解くと、意外な事実や謎が浮かび上がってきます。この記事では、神武天皇陵の変遷、そして「再発見」の物語に迫り、初代天皇をめぐる歴史のロマンに触れてみましょう。
江戸時代:忘れ去られた陵墓、そして候補地の選定
平和な時代が訪れた江戸時代。人々の関心が歴史へと向けられるようになると、忘れ去られていた神武天皇陵の探索が始まりました。古事記や日本書紀には畝傍山の北ないし東北に位置すると記されていましたが、具体的な場所は不明瞭でした。
候補地として挙がったのは、畝傍山東北裾野にある塚山、丸山、そして神武田の3ヶ所。しかし、決定的な証拠はなく、幕府による修陵事業では塚山に仮に定められました。(現在は綏靖天皇陵となっています。)
幕末の再治定:水田から天皇陵へ
幕末、天皇の存在感が高まる中で、神武天皇陵の場所が再検討されることになります。1863年、幕府は勅裁に基づき神武天皇陵を神武田に変更しました。驚くべきことに、この場所はかつて水田、それも人糞を用いる糞田だったという記録が残っています。糞田から天皇陵への劇的な変化は、歴史のダイナミックさを物語っています。
 神武天皇陵の現在の様子
神武天皇陵の現在の様子
明治時代:近代化と整備、そして現在の姿へ
明治時代に入ると、神武天皇陵の整備はさらに進められました。1898年には周濠の中に円墳が築かれ、古墳としての体裁が整えられました。そして、皇紀2600年には大規模な整備が行われ、現在のような堂々たる姿になったのです。
丸山落選の理由:被差別部落の存在
有力候補地であった丸山が落選した背景には、近くに被差別部落があったためと言われています。この事実は、当時の社会状況を反映するものであり、歴史を考える上で重要な視点を与えてくれます。
 神武天皇陵の周辺地図
神武天皇陵の周辺地図
神武天皇陵:歴史の謎とロマン
神武天皇陵の歴史を辿ると、様々な時代の変化や社会背景が浮かび上がってきます。古事記や日本書紀の記述、江戸時代の探索、幕末の再治定、そして明治時代の整備。それぞれの時代に、神武天皇陵に対する人々の思いが込められています。
歴史学者である山田一郎氏(仮名)は、「神武天皇陵の変遷は、日本の歴史そのものを象徴していると言えるでしょう。陵墓の謎を解き明かすことは、日本のルーツを探る旅でもあるのです」と語っています。
神武天皇陵は、単なるお墓ではなく、日本の歴史と文化を理解する上で重要な場所です。その歴史に触れることで、私たちは日本のルーツへの理解を深め、未来への道を切り開くヒントを得ることができるでしょう。