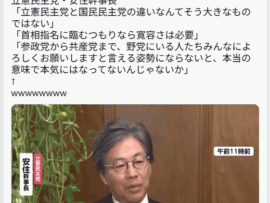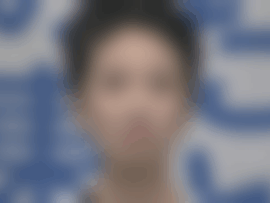政府の中央防災会議が発表した最新の南海トラフ地震の被害想定は、私たちに改めて自然災害の脅威を突きつけています。最大震度7、マグニチュード9級の巨大地震が発生した場合、最悪で29万8000人もの尊い命が失われ、経済的損失は292兆円にものぼると予測されています。これは、前回の2012~13年の想定を上回る深刻な数字です。
津波による被害が甚大、早期避難が生死を分ける
今回の想定では、福島県から沖縄県までの広範囲で3メートル以上の津波が襲来すると予測されており、特に高知県黒潮町と土佐清水市では最大34メートルもの津波が押し寄せる可能性があります。津波による死者は21万5000人と全体の7割を占め、改めて津波の脅威が浮き彫りとなりました。報告書でも「津波からいち早く避難することが、一人ひとりの命を守るためには必要不可欠」と強調されており、日頃からの備えと迅速な避難行動が生死を分ける鍵となります。
 alt
alt
冬の深夜発生を想定、被害は最大規模に
今回の想定では、在宅者の多い冬の深夜に地震が発生し、津波からの早期避難率が20%と低いケースを想定しています。さらに、人口の多い東海地方での被害が大きいことも加わり、被害は最大規模に達すると予測されています。負傷者数は最大95万人、避難者数は最大1230万人にも及ぶとされており、その甚大さは想像を絶します。
東日本大震災や能登半島地震を参考に、災害関連死も試算
今回の想定では、東日本大震災や2023年の能登半島地震の経験を踏まえ、災害関連死についても初めて試算が行われました。その結果、2万6000人から5万2000人の災害関連死が発生する可能性があると予測されています。 これは、地震や津波による直接的な被害だけでなく、避難生活の長期化による健康悪化や、医療体制の逼迫など、間接的な被害の深刻さを示すものです。
「半割れ」ケースも想定、更なる被害拡大の可能性
南海トラフ地震では、過去の地震の傾向から、震源域の東側と西側でマグニチュード8級の地震が時間をおいて発生する「半割れ」ケースも想定されています。この場合でも死者数は最大17万6000人に達すると予測されており、被害の拡大が懸念されます。
専門家の声:防災意識の向上と地域連携が重要
防災専門家の山田太郎氏(仮名)は、「今回の想定は、南海トラフ地震の甚大な被害を改めて示すものだ。一人ひとりが防災意識を高め、日頃から避難経路の確認や防災グッズの準備など、具体的な対策を進めることが重要だ。また、地域住民同士の連携強化や、行政との協力体制の構築も欠かせない」と指摘しています。
防災対策の強化と減災目標の見直しへ
政府は今回の報告書を踏まえ、2014年に策定した南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しを進める方針です。ハード面の整備だけでなく、住民の防災意識の向上や避難体制の強化など、ソフト面の対策も強化していく必要があります。

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくない切迫した脅威です。私たちは、この想定を他人事と思わず、日頃から防災対策を徹底し、万が一の事態に備える必要があります。