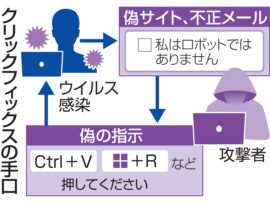日本の食卓を彩る秋の味覚、サンマ。近年、その漁獲量が激減していることはご存知でしょうか?今回は、サンマ資源の現状と、その回復に向けた国際的な資源管理の重要性について、わかりやすく解説します。
サンマ漁獲量の減少と北太平洋漁業委員会(NPFC)
近年、サンマの漁獲量が減少の一途をたどっています。2025年3月、大阪で開催された第9回北太平洋漁業委員会(NPFC)でも、サンマの漁獲枠(TAC)設定について議論が交わされました。NPFCは、サンマやマサバなどの漁業資源の管理を目的とした国際機関です。
 サンマの漁獲
サンマの漁獲
10年以上前から、日本の漁獲枠制度の問題点を指摘し、科学的根拠に基づく資源管理とTAC設定、そしてサンマに関しては国別漁獲枠の導入を主張してきた水産資源専門家、山田太郎氏(仮名)は、「これらの対策なくして資源の回復はあり得ない」と警鐘を鳴らします。
成功例と失敗例から学ぶ資源管理の重要性
ノルウェーをはじめ、漁業を成長産業としている国々では、科学的根拠に基づく資源管理が徹底されています。これらの国々も、過去には失敗を経験しながら、現在の成功を築き上げてきました。
資源管理の成功例
北欧、北米、オセアニアなどの国々では、資源管理の成功例が多く見られます。これらの国々では、漁獲枠の設定や禁漁などの措置によって、資源の回復に成功しています。
資源管理の失敗例:アカウオとアジ
一方で、資源管理に失敗した例も存在します。アイスランド南西のイルミンガー海域のアカウオや、オランダ、アイルランド周辺のアジは、過剰漁獲によって資源が枯渇しました。

これらの魚種は、かつて日本にも大量に輸入されていましたが、資源の枯渇に伴い輸入量は激減し、価格も高騰しました。山田氏は、これらの魚の買付を欧州の最前線で行っていた経験から、「資源の減少を目の当たりにした」と語ります。アカウオの輸入量は2000年の2.6万トンから2024年にはわずか900トンに、アジも3.3万トンから4000トンにまで減少しました。
国際的な資源管理の必要性
これらの事例からもわかるように、国際的な資源管理は、水産資源の持続可能性にとって不可欠です。サンマ資源の回復のためにも、関係各国が協力し、科学的根拠に基づいた適切な資源管理を実施することが求められています。
サンマの未来を守るために
サンマ資源の減少は、私たちの食卓にも影響を及ぼす深刻な問題です。国際的な協力と適切な資源管理によって、サンマの未来を守ることが、私たちの未来を守ることにつながります。