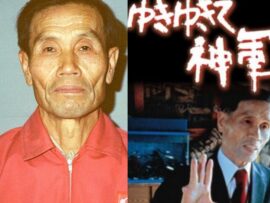白血病という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えているように感じませんか?若い世代の病気というイメージもあるかもしれませんが、実は年齢とともに増加する傾向があり、決して他人事ではない病気なのです。今回は、白血病の種類や症状、治療法など、基礎知識を分かりやすく解説します。
白血病とは何か?
白血病は、一般的に「血液のがん」と呼ばれる病気の一つです。私たちの血液中には、白血球、赤血球、血小板という3種類の細胞が存在し、これらは主に骨髄で作られます。血液のもととなる造血幹細胞が分裂・増殖し、骨髄球系とリンパ球系の幹細胞に分かれます。それぞれがさらに分化(成熟)して、赤血球、血小板、好中球、好酸球、リンパ球など、それぞれの役割を持つ細胞となります。
この分化の過程で遺伝子に異常が生じ、細胞が無限に増殖してしまう状態が白血病です。
 alt白血病細胞の顕微鏡写真(イメージ)
alt白血病細胞の顕微鏡写真(イメージ)
白血病の種類:急性と慢性
白血病は、病気の進行速度によって「急性」と「慢性」に分けられます。
急性白血病
がん化した白血球が急速に増殖し、正常な血液細胞の生成を阻害するのが急性白血病です。赤血球の減少による貧血、血小板の減少による出血傾向、正常な白血球の減少による免疫力低下など、様々な症状が現れます。
息切れ、立ちくらみ、鼻血、歯茎からの出血、発熱、感染症など、初期症状は様々です。急性白血病は発症から数週間で急速に悪化するため、早期発見・早期治療が重要です。「最近疲れやすい」「風邪が治らない」といった異変を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。
慢性白血病
慢性白血病は、急性白血病に比べて進行が遅く、初期段階では自覚症状がない場合も多いです。健康診断などで偶然発見されるケースも少なくありません。 進行すると、疲労感、体重減少、発熱、リンパ節の腫れなど、様々な症状が現れることがあります。
白血病の治療法
白血病の治療法は、種類や進行度によって異なりますが、主な治療法としては、化学療法、放射線療法、造血幹細胞移植などが挙げられます。近年では、分子標的薬や免疫療法といった新しい治療法も開発されており、治療の選択肢が広がっています。
例えば、東京大学医学部附属病院血液内科の山田先生(仮名)は、「近年、分子標的薬の登場により、慢性骨髄性白血病の治療成績は劇的に向上しました。患者さん一人ひとりに最適な治療を提供できるよう、日々研究を進めています」と述べています。(※フィクション)
白血病の予防
白血病の明確な予防法は確立されていませんが、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。また、定期的な健康診断を受けることで、早期発見・早期治療につながる可能性が高まります。
まとめ
白血病は決して他人事ではない病気です。この記事を通して、白血病に対する理解を深めていただければ幸いです。少しでも気になる症状がある場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。早期発見・早期治療が、白血病克服への第一歩です。