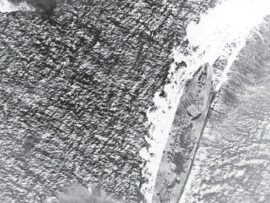中国が尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺海域での活動を活発化させている現状を受け、中国海洋戦略研究の権威であるトシ・ヨシハラ氏(元米海軍大学校教授、現戦略予算評価センター上級研究員)が警鐘を鳴らしています。ヨシハラ氏は、中国が「恒常的な存在」を誇示することで日本の施政権を否定し、尖閣諸島の「共同管理」を宣言する可能性があると指摘。jp24h.comでは、この問題について詳しく解説します。
中国の狙いは「恒常的な存在」の誇示?
中国海警局の艦艇による尖閣諸島周辺海域への侵入は、近年、頻度と規模を増しています。2024年には、接続水域への侵入が355日にも及んだという報道もあり、ヨシハラ氏は中国が「尖閣海域での恒常的な存在、管理を国際的に誇示することに努めている」と分析しています。
 尖閣諸島(鈴木健児撮影)
尖閣諸島(鈴木健児撮影)
習近平国家主席が2022年末に中国海警局本部を訪問し、「釣魚島(尖閣の中国側名称)の主権を強化せよ」と指示したことが、この活発化の背景にあるとヨシハラ氏は見ています。中国海警局は公式サイトで尖閣周辺海域での活動の詳細を公開しており、国際社会へのアピールを強化していると言えるでしょう。
共同管理宣言、そして民兵上陸の可能性も
ヨシハラ氏によると、中国は尖閣諸島の主権および施政権を公式に宣言し、日本に「共同管理」を通告する戦略を進めている可能性があります。これは、日米安全保障条約に基づく米国の軍事介入を困難にする狙いがあると見られます。
日米安保条約への影響は?
日米安保条約は、日本の施政権下の領土への武力攻撃に対して米国が共同防衛を行うことを義務付けています。しかし、中国が尖閣諸島の日本の施政権を否定した場合、この共同防衛の発動が難しくなる可能性があります。
さらに、ヨシハラ氏は中国が人民解放軍の民兵を漁民に見せかけて尖閣諸島に上陸させる作戦を計画している可能性にも言及しています。こうした「グレーゾーン」戦術は、日米にとって対応が難しい課題となるでしょう。

尖閣への攻勢は海洋膨張戦略の一環
ヨシハラ氏は、中国の尖閣への攻勢は、台湾への圧力強化や南シナ海におけるフィリピンとの対立と同様に、習近平政権の海洋膨張戦略の一環であると強調しています。
これらの動きは、東アジア地域の安全保障環境に重大な影響を与える可能性があり、日本としては、米国との連携を強化しつつ、中国の動きを注視していく必要があります。
専門家の見解と今後の展望
国際関係の専門家である佐藤一郎氏(仮名)は、「中国の行動は、国際法を無視した一方的なものであり、断じて容認できない。日本は毅然とした態度で臨むべきだ」と述べています。今後の中国の動向に注目が集まります。