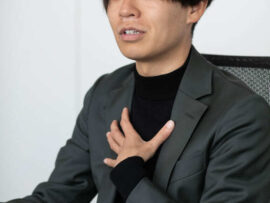この記事では、平城京・平安京の時代から続く「里子村」で育った最後の里子、A子さん(仮名)の体験談を通して、昭和50年代の里子制度の厳しい現実をご紹介します。A子さんの幼少期から小学校卒業までの共同生活は、想像を絶する過酷なものでした。当時の生活の様子を紐解きながら、里子制度の課題について考えてみましょう。
震える手で雑巾がけ…温かい布団で眠る家の子どもたちとの格差
A子さんは毎朝、お寺の本堂から縁側まで雑巾がけをするのが日課でした。真冬でも冷たい水を使用し、手がかじかんで震えながらも作業を続けなければなりませんでした。同じ屋根の下で暮らすお寺の家の子どもたちは暖かい布団でぐっすり眠っている中、里子であるA子さんだけがこの重労働を強いられていました。このような差別的な扱いは、幼いA子さんの心に深い傷を残したに違いありません。
 alt
alt
ドアもないトイレ、満足に洗えない髪…衛生環境の劣悪さ
トイレは屋外に掘られただけの穴で、ドアもなくプライバシーは全く守られていませんでした。便器もないため、排泄物で汚れた穴に落ちる恐怖と常に隣り合わせでした。お寺の家の人たちは水洗トイレを使っていたそうですが、A子さんは一度もそれを使うことを許されませんでした。入ることすら禁じられていたのです。幼い子どもにとって、清潔な環境で安心して用を足せることは当然の権利であるはずです。しかし、A子さんはその権利さえも奪われていたのです。入浴も幼稚園の頃から一人で済ませるように言われ、正しい洗い方も分からず、髪を左右半分ずつ洗っていたといいます。
食料も衣服も満足に与えられず…常に空腹と隣り合わせの生活
A子さんは常に空腹に悩まされていました。満足に食事を与えられなかったため、お店から食べ物をくすねたり、友達の家から持ってきたり、ゴミ箱を漁ることもあったといいます。お店で見つかって叱責されても、どんなに哀願しても食べ物を分けてもらえることはありませんでした。衣服も満足に与えられず、同じパンツを裏返して履き続けることもありました。友達のお母さんに汚いと指摘されても、新しいパンツは持っていませんでした。靴も小さくなって痛むと訴えても、2サイズも大きい靴を買ってきて、小学6年生まで履くように言われました。大きすぎて履けず、結局小さい靴を履き続け、穴が開いてしまうほどでした。

里子たちの世話は年長の子どもに押し付けられ…突然の失踪劇
A子さんの面倒を見ていたのは、お寺の「おばあちゃん」ではなく、年長の子どもたちでした。まだ小学生だったお兄ちゃんたちは、A子さんの世話をすることを強いられていました。中学を卒業すると近所で働き始めましたが、ある日突然、村から姿を消してしまいました。子どもたちに子どもを育てさせるという無責任な体制は、里子たちにとって大きな不安定要因となっていたと言えるでしょう。児童福祉の専門家、佐藤先生(仮名)は、「里親家庭における子どもの適切なケアと教育は、里親自身の養育能力に加え、行政による継続的な支援が不可欠です。A子さんのケースは、まさにその支援が欠如していた典型例と言えるでしょう」と指摘しています。
A子さんの証言から学ぶ里子制度の課題
A子さんの体験は、昭和50年代の里子制度が抱えていた問題点を浮き彫りにしています。十分な食事、清潔な衣服、適切な教育、そして愛情のこもったケア。これらはすべて、子どもが健やかに成長するために不可欠なものです。A子さんの証言は、私たちに里子制度のあり方について改めて問いかけています。現代社会においても、里子や養子縁組といった制度を利用する子どもたちが安心して暮らせるよう、社会全体で支援していく必要があるのではないでしょうか。
A子さんのような悲しい経験をする子どもたちが一人でも減ることを願って、この記事を締めくくりたいと思います。