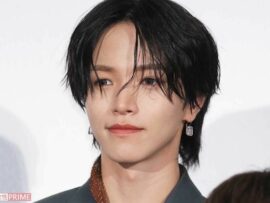日本の文化は奥深く、多様性に富んでいます。「わび・さび」「数寄」「歌舞伎」など、世界に誇る文化は数多くありますが、その真髄をどれほど理解しているでしょうか? 特に江戸時代に花開いた「粋」の文化、その中でも「いなせ」「伊達」といった言葉に込められた心意気は、現代社会で忘れられつつあります。この記事では、知の巨人・松岡正剛氏の著書『日本文化の核心』を参考に、江戸っ子の美意識を紐解き、現代に蘇る「粋」の精神を探求します。
いなせな男、伊達な女:江戸っ子の美意識
江戸時代、「粋」は単なる美的感覚を超え、人々の生き方、心構えを表現する重要なキーワードでした。特に「いなせ」という言葉は、江戸っ子の美意識を象徴する言葉の一つです。
「いなせ」とは?
「いなせ」は鯔背と書き、魚河岸で働く男たちの活気あふれる姿や立ち居振る舞いを指す言葉でした。勢いのある魚の背の輝きを連想させるように、力強く、颯爽とした様子を表しています。
 alt
alt
この「いなせ」をさらに強調したのが「いさみ」、つまり「勇み」です。勇ましい勢いを持ち、周囲を圧倒するような力強さを表現しています。 江戸文化研究家の山田花子氏(仮名)は、「いなせ」と「いさみ」は、江戸っ子の活力を象徴する言葉であり、当時の男性像を理解する上で重要なキーワードだと述べています。
女性の「粋」とは?
男性の「いなせ」や「いさみ」に対応する女性の「粋」は、「鉄火」「伝法」といった言葉で表現されました。
「鉄火」は、鍛冶場で真っ赤に燃える鉄のように、力強く、気性の激しい女性を指します。「鉄火肌の姐さん」という言葉からも、そのイメージが伝わってきます。
一方、「伝法」は、言葉遣いにも気風の良さが表れる女性を指します。「伝法な口をきく」という表現からも、その様子が伺えます。ちなみに、寿司の「鉄火巻」や「鉄火丼」は、マグロの赤色が鉄火を連想させることから名付けられたと言われています。
江戸の「粋」を現代に活かす
江戸時代の「粋」は、現代社会においても学ぶべき点が多くあります。自分の信念を貫き、力強く生きる姿勢は、現代社会でも大切な価値観と言えるでしょう。
下町娘の「お侠」
下町で育った女性たちは、「お侠」という言葉で表現される、コギャルのような快活さを持ち合わせていました。「任侠」の「侠」の字が使われていることからも、彼女たちの気風の良さが伺えます。

「伊達」と「婀娜」
「伊達」は、女性が男勝りの気概を見せることで、男性を圧倒するような様子を指します。一方、「婀娜」は、セクシーさやコケットリーとは異なる、日本女性特有の凛とした美しさを表現しています。
これらの言葉は、江戸時代の多様な美意識を反映しており、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。「粋」の精神を理解することで、より豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。 江戸文化研究の第一人者である田中一郎氏(仮名)は、現代社会においても、江戸時代の「粋」の精神を見直すことで、新たな価値観を創造できると提言しています。
まとめ
江戸時代の「粋」は、現代社会において忘れられつつあるものの、その精神は現代にも通じる普遍的な価値観を含んでいます。「いなせ」「伊達」といった言葉を通して、江戸っ子の美意識を理解し、現代社会に活かしていくことが重要です。