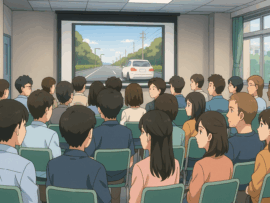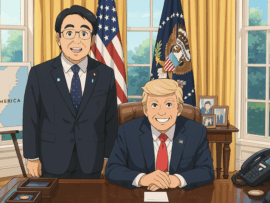外務省のホームページに掲載された「中国への修学旅行相互受け入れ促進」という表現をめぐり、波紋が広がっています。2018年12月、当時の岩屋毅外相と中国の王毅外相との間で合意されたこの件について、国会で疑問の声が上がりました。jp24h.comでは、この問題について詳しく解説します。
外務省HPの「促進」という表現に批判
日本維新の会の西田薫衆院議員は、外務省HPの「修学旅行の相互受け入れ促進」という表現に対し、「中国へ行ってくださいと誤解を与える。『促進』という言葉は違う」と批判しました。西田議員は、中国で発生した日本人児童の死傷事件を例に挙げ、安全確保の観点から疑問を呈しました。
 alt西田薫衆院議員(左)と岩屋毅外相
alt西田薫衆院議員(左)と岩屋毅外相
岩屋前外相の釈明「個々の学校への要請ではない」
これに対し、岩屋前外相は「日本の個々の学校に対して、中国への修学旅行の実施を求めることではない」と釈明。「希望する学校に政府として安全確保の面で可能な支援を行うものだ」と説明しました。しかし、西田議員は「日中両国の障壁を政府が取り除いた上で、双方が嫌な思いを持っていないような状況になってから、子供たちに行ってもらうべき」と反論しました。
中国での安全確保に懸念の声
西田議員は、岩屋前外相が国会質疑で、中国当局による修学旅行生の警備について言及したことに対しても、「現地でしっかりとした警備が必要な場所に行くことがそもそも違うのではないか」と批判。中国における安全確保に対する懸念を改めて表明しました。 日本の旅行業界専門家、佐藤一郎氏(仮名)も「安全面での懸念が払拭されない限り、修学旅行先として中国を選ぶ学校は少ないだろう」と指摘しています。
外務省HPの表現見直しへ
一連の批判を受け、岩屋前外相は「ホームページの書きぶりがどうあるべきかは、指摘を踏まえて検討したい」と応じました。この問題は、自民党の有村治子元女性活躍担当相も国会で取り上げるなど、今後の動向が注目されます。
まとめ:中国への修学旅行、安全確保と相互理解が不可欠
中国への修学旅行促進をめぐる議論は、安全確保の重要性と日中間の相互理解の必要性を改めて浮き彫りにしました。外務省は、HPの表現を見直すとともに、国民の不安解消に向けた取り組みが求められます。今後の展開に注目が集まります。