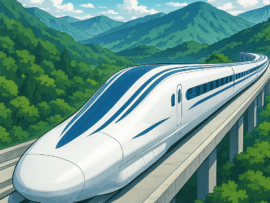[ad_1]
SNSで客に対する不満をぶちまけ、炎上する飲食店が増えている。グルメジャーナリストの東龍さんは「予約困難店が増え、売り手優位の風潮が強まったせいで、飲食店が客を軽視するようになっている。客と店が互いに敬意を払わなければ食文化は育たない」という――。
■Threadsで客に文句を言う飲食店アカウント
Meta社が運営するSNS「Threads(スレッズ)」が、飲食店関係者の“毒”を吐く場所として盛り上がっている。Xほどユーザー数が多くないため、広くメディアに取り上げられるような炎上にはまだつながっていないが、Threads内で物議を醸すことはしょっちゅうだ。
そこで吐き出される“毒”の多くは、客への不満だ。
お酒が飲めない客やドリンクの注文が少ない客に対して「二度と来るな」と怒りを発したり、お通しのわずかな金額を嫌がる客に「家でご飯を食べていろ」とあしらったり、客グループの“下っ端”がお冷を人数分頼むことに対して「気を利かせたつもりかもしれないが、本当に仕事ができる人なら店員にも気を利かせられるはず」と文句を言ったりと、内容はさまざま。
なかには、飲食店経営者を名乗るアカウントが「自分は客に『ありがとうございます』は言わない」と投稿して、Threads内で話題になったケースもある。投稿者は「金をもらっているがその金額以上の価値のサービス、商品を提供しているので客より立場は上」「感謝されるのはこちら側」とも述べており、批判のリプライが殺到。ちょっとした炎上状態となった。
■カスハラ客に対応して鬱憤を貯めている可能性
「ありがとう」を言わない店は論外だが、その他の投稿は飲食店の側に立てば事情は理解できる内容ではある。また、中には炎上マーケティングを意図してあえて極端なことを言っているアカウントもあると考えられる。
しかし、こうした投稿を日々目にしていて感じるのは、「客を軽視する飲食店が増えている」ということだ。その背景にはいくつかの構造的な要因がある。
まず前提として、飲食業界の慢性的な人手不足により、接客の質が落ちている点。そして、厄介な客が増えていることも無関係ではないはずだ。
「カスタマー・ハラスメント」という言葉が世間で定着しつつある。東京都は、2024年10月4日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(カスハラ防止条例)を制定し、2025年4月1日から施行した。飲食店でもカスタマー・ハラスメントは多く、「飲食店ドットコム」が行った調査によると、回答者の約55.7%が「カスハラを受けた経験がある」という。
客の理不尽な要求に対するストレスや過剰反応が、前述のような過激な発言の引き金になっているところはあるだろう。
■予約困難店が激増して売り手優位の構造ができた
だが、より本質的なのは、飲食店の立場が変わりつつあることだ。
ミシュランガイド三つ星を有する京料理の老舗「菊乃井」の三代目・村田吉弘氏が、飲食店が高額化かつ予約困難化している風潮に疑義を呈し、飲食業界や食通の間で話題になった。
村田氏は、「高額=上等」と考える一部の客がスタンプラリーのように話題の店を回り、無名の店まで予約困難にし、価格を押し上げていると指摘。その結果として、実績のない若手が京都で開業して客から2万5000円をとったり、肌感覚としてはかつては3〜4万円程度だった東京の鮨店が7万円になったりするような事態になっているという。
日本のファインダイニングは、ミシュランガイドでも世界的に星が多く、アジアのベストレストラン50でも評価が高い。日本料理や鮨、鉄板焼といったジャンルに限らず、日本のファインダイニングは海外の富裕層から支持を得ている。一休、OMAKASE、食オク!、Foodies Primeといった、予約困難店に特化した飲食店予約サービスも増えた。こうした状況が「飲食店が客を選ぶ」空気感を強めていることは否めない。
SNSで客を見下すような発言をしているのは、ファインダイニングよりもカジュアルな業態のほうが多いように思われる。ただ、そうした業態であっても、グルメサイトの発展や予約サイトの普及によって予約困難化し、“売り手優位”になっている飲食店は少なくない。
また、飲食業界は師弟関係をはじめとして上下関係が強く、スターシェフやトップレストランはほかの飲食店に大きな影響を与える。一部のファインダイニングによる客を軽視する姿勢や売り手市場による優位感が、カジュアルな業態にも浸透し、上から目線を生むことにつながると考えられる。
[ad_2]
Source link