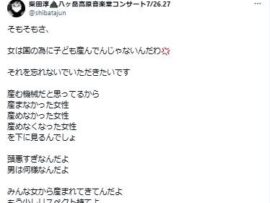福岡市営地下鉄には、一度も使われたことのない「幻の改札口」が存在することをご存知でしょうか?開業以来、静かにその役割を待ち続ける臨時改札口。今回は、その知られざる歴史と存在意義に迫ります。
40年以上使われていない「幻の改札口」
西日本新聞「あなたの特命取材班」に寄せられた情報によると、福岡市営地下鉄には一度も利用客が通ったことのない改札口が存在するとのこと。調査の結果、千代県庁口駅と箱崎宮前駅にその「幻の改札口」が確認されました。
 千代県庁口駅の臨時改札口
千代県庁口駅の臨時改札口
これらの改札口は、自動改札機とは異なり、小舟のような形状をした有人改札口。福岡市交通局によると、千代県庁口駅は1984年、箱崎宮前駅は1986年の開業時に、それぞれ臨時改札口として設置されたとのことです。
神社の参拝客対策として設置された背景
両駅の近くには、古くから博多っ子に親しまれている十日恵比須神社と筥崎宮があります。初詣や正月大祭、放生会など、多くの参拝客が訪れる際に駅が混雑することが予想され、スムーズな乗降を確保するために臨時改札口が設置されました。

しかし、実際には自動改札機で十分対応できたため、臨時改札口が使われる機会はありませんでした。現在ではICカードやクレジットカードでのタッチ決済が主流となり、交通局担当者も「今後、有人改札口を使う機会はもうないのではないか」と語っています。
災害時の避難路としての役割
では、なぜこれらの臨時改札口は撤去されないのでしょうか?それは、災害発生時の避難路としての役割を担っているからです。臨時改札口はホーム端の非常階段につながっており、緊急時には避難経路や消防隊の進入路として活用される想定となっています。
都市防災の観点からも重要な存在
交通局によると、幸いにもこれらの改札口が実際に使用されたケースはありません。しかし、都市防災の専門家である(仮称)佐藤教授は、「これらの臨時改札口は、有事の際に人命を守る上で非常に重要な役割を果たす可能性がある。存在自体が安心感につながる」と指摘しています。
“使われない”からこそ価値がある
一度も使われたことのない「幻の改札口」。それは、福岡市営地下鉄の安全が守られてきた証であり、都市防災への備えの象徴とも言えるでしょう。一見無駄に見えるものにも、重要な役割が隠されている。そんな視点を持つことで、私たちの街の安全安心に対する理解が深まるのではないでしょうか。