今後30年以内に80%程度の確率で発生が想定され、最大で29万8000人もの死者が出ると予測されている南海トラフ巨大地震。政府は7月1日、この壊滅的な被害を想定し、死者数を8割削減することを目指す新たな防災計画を決定しました。しかし、2014年に策定された前回の防災計画でも同様の目標が掲げられ、様々な対策が進められたにもかかわらず、その実現には至っていません。大地震やそれに伴う巨大津波から命を守るためには、私たちは具体的にどのような対策を講じるべきなのでしょうか。本記事では、南海トラフ巨大地震への備えと、東日本大震災での実際の被災体験から得られる教訓を探ります。
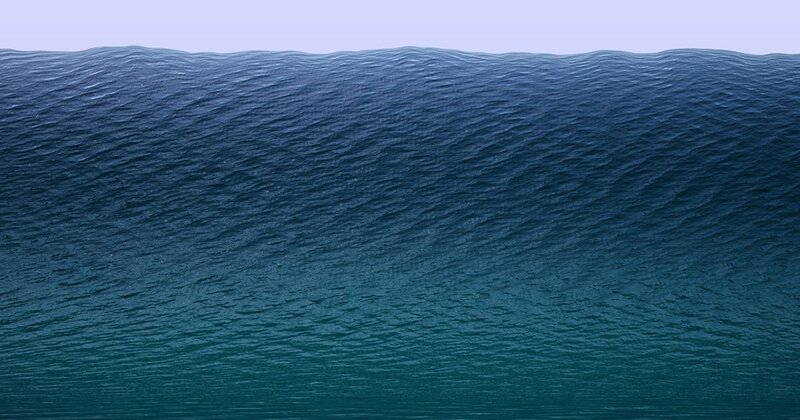 南海トラフ巨大地震による沿岸部の津波被害を想定したイメージイラスト – 防災計画関連ニュース
南海トラフ巨大地震による沿岸部の津波被害を想定したイメージイラスト – 防災計画関連ニュース
東日本大震災の現場から見えた「生死を分けた行動」
大手放送局に勤務する秋元美樹氏は、2011年の東日本大震災発生直後から被災地に入り、精力的に取材を重ねてきました。多くの被災者の生々しい体験談を聞く中で、命が助かった人々とそうではなかった人々の間で、いかに些細な、あるいは決定的な「行動」が生死を分けたかが浮かび上がってきたと言います。ここでは、奇跡的に生還を果たした、ある60代男性の証言を振り返ります。
運転中に巨大津波が迫る恐怖
あの日、宮城県の沿岸部に住むその男性は、いつものように国道を車で走らせていました。しかし、日常は突然、非日常へと変わります。地面が激しく揺れ、地鳴りが響き渡り、男性はただ必死にハンドルにしがみつくことしかできませんでした。なんとか車を路肩に停め、深く呼吸をしてからラジオをつけました。耳を疑うような「大津波警報」という言葉が、何度も繰り返されていました。
その時点では、津波が到達するまでまだ30分以上の時間がありました。「まだ大丈夫だろう」と男性は考え、そのまま車を走らせ続けることにしました。
しばらくすると、視界の端に何か異様なものが入ってきました。それは、海の方から猛烈な速さで近づいてくる、まるで黒い壁のような巨大な津波でした。「なんか映画の一場面みたいだな…」あまりに現実離れした光景だったためか、妙に冷静だったといいます。
津波まではまだ距離がある。まだ逃げられる。男性はアクセルを強く踏み込もうとしました。しかし、その瞬間、男性の体が突然、急回転したのです。そして次の瞬間、まるで鉄の塊にぶつかったような、想像を絶する激しい衝撃に襲われました。「いったい何が起きたのか、全く状況がつかめない」。「痛い」という言葉さえ口にする余裕がないことだけは本能的に理解しました。漆黒の津波は、すぐ目前にまで迫っていました。
死を覚悟した絶体絶命からの奇跡
実はこの時、巨大津波は凄まじい強風を巻き起こしながら押し寄せていました。津波は大量の空気を前方に押し出すため、津波本体に先行して突風が発生することがあります。男性は、その突風によって車ごと宙に浮き上がり、近くの建物に叩きつけられて横転していたのです。自然災害には、人間の予測や常識をはるかに超える、未解明の脅威がいくらでも存在します。「津波が来てから逃げればいい」という安易な考え方自体が、いかにおこがましく、そして危険であるかをこの体験は示唆しています。
ゴボゴボゴボ……横転した車内に不気味な水の音が響き渡ります。音の方に目をやると、車の隙間から真っ黒な海水が勢いよく浸入してきていました。あっという間に膝の高さまで水が浸かってしまいました。「早く脱出しないとまずい」。男性は焦ってシートベルトを外そうと、バックルに手をかけ、強く押しました。しかし、全く外れません。もう一度、渾身の力で押してみますが、やはり外れないのです。
ゴボゴボゴボ……ひんやりとした鈍い感覚が、男性の背筋をなぞりました。「人間ってこうやって死ぬんだな」。完全に死を覚悟した男性でしたが、この直後に取ったある「行動」によって、九死に一生を得る奇跡的な生還を果たすことになります。
教訓:自然の脅威を過小評価せず、即座に行動することの重要性
この男性の体験談は、南海トラフ巨大地震のような未曽有の災害に直面した際に、いかに状況が瞬時に悪化し、予期せぬ事態が発生するかを生々しく物語っています。「まだ大丈夫」という判断の遅れが、どれほど致命的になりうるか。そして、津波だけでなく、それに先行する強風のような複合的な脅威が存在すること。さらに、車が横転し、シートベルトが外れないといった、通常では考えられないような状況下でも、諦めずに「行動」を起こすことが生死を分ける可能性があること。これらの教訓は、政府の防災計画による対策だけでなく、私たち一人ひとりが自然の脅威を過小評価せず、警報が出された際には躊躇なく、そして即座に避難行動を開始することの極めて重要な意味を浮き彫りにしています。






