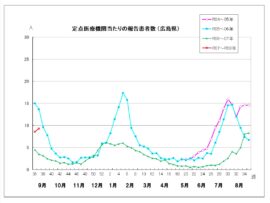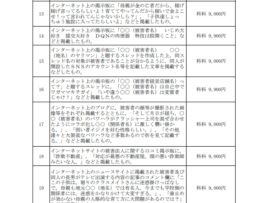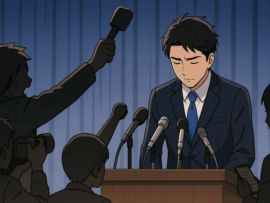提供精子や卵子を使って生まれた子どもの「出自を知る権利」を保障する法案が議論を呼んでいます。一見、権利保障を進めるように見えるこの法案ですが、本当に子どもたちの権利を守れるのでしょうか?当事者からは、この法案への強い反発の声が上がっています。この記事では、法案の問題点、そして本当に子どもたちにとって必要な保障とは何かを探っていきます。
出自を知る権利:法案の現状と課題
2024年2月、特定生殖補助医療法案が提出されました。この法案は、提供精子や卵子を使った生殖補助医療の制度を定め、子どもの出自を知る権利を保障することを目的としています。しかし、この「保障」には大きな落とし穴があるという指摘が相次いでいます。
 alt
alt
法案では、提供者の情報は18年間、国立成育医療研究センターに保管されることになっています。しかし、子どもが情報にアクセスするためには、提供者の同意が必要となるのです。提供者が同意しなければ、子どもは自身のルーツを知る術がありません。これは、出自を知る権利を真に保障していると言えるのでしょうか?
立憲民主党の阿部知子衆議院議員は、この問題点を強く批判しています。子どもたちは、自身の半分を形成する存在について、18歳まで何も知ることができない可能性があるのです。これは子どもたちのアイデンティティ形成に大きな影響を与えかねません。
当事者の声:本当に必要な保障とは
提供精子・卵子で生まれた子どもや、その親たちで構成される「ふぁみいろネットワーク」も、この法案に強い懸念を示しています。彼らは、真の権利保障のためには、提供者の同意の有無に関わらず、子どもが情報にアクセスできる仕組みが必要だと訴えています。
「ふぁみいろネットワーク」の鈴木ひとみさんは、法案の問題点を具体的に指摘しています。提供者の匿名性を守ることと、子どもの出自を知る権利を両立させるためには、より精緻な制度設計が必要不可欠です。
専門家の見解:法案の憲法適合性への疑問
著名な憲法学者である山田太郎教授(仮名)は、「提供者の同意を必要とする規定は、憲法で保障されている自己決定権に抵触する可能性がある」と指摘しています。子どもたちは、自身に関する情報を知る権利を、他者の意思によって制限されるべきではないのです。
未来への展望:子どもたちの権利を守るために
提供精子や卵子による生殖補助医療は、不妊に悩むカップルにとって大きな希望となる技術です。しかし、同時に、生まれてくる子どもの権利についても十分に配慮する必要があります。
真に子どもたちの権利を守るためには、提供者の匿名性と子どもの出自を知る権利のバランスをどのようにとるのか、社会全体で真剣に議論していく必要があります。
提供精子・卵子で生まれた子どもたちが、自身のルーツを知り、健やかに成長できる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを考えていきたいですね。