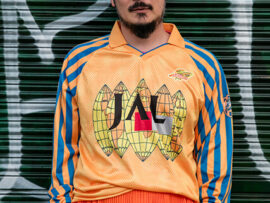メンタルヘルスの不調は、誰にでも起こり得る。不調を抱えたとき、仕事への“休職”や“復職”を考える際に必要となってくるのが、医師からの「診断書」だ。どのような種類の診断書があり、どんなタイミングで会社へ提出すればよいのか。1万人以上の社員たちと面談してきた産業医が解説する。※本稿は、武神健之『未来のキャリアを守る 休職と復職の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を抜粋・編集したものです。
● 産業医が重要視する 5種類の診断書
診断書とは、治療医から会社に出される公式文書です。職場のメンタルヘルス関連では、診断書の内容は社員の就業上の配慮、休職や復職など主治医の判断を会社に伝えるために提出されます。
もちろん、会社側の要望で、産業医(編集部注/事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師)が主治医に診断書を求めることもあります。
診断書の発行手数料は保険診療ではありませんので、だいたい1回2000円から5000円ぐらいと医療機関により違いがあります。そのため、不要な診断書は書いてもらわない、書いてもらう診断書は意味のある診断書にするほうがいいでしょう。
そして大切なことですが、診断書が出たら、自分の医療記録として会社に提出前に写真を撮って保存しておきましょう。また、いずれも診断書は上司ではなく、人事に渡しましょう。そして、診断書とともに産業医面談を受けることをおすすめします。
私は産業医として様々な診断書を見てきました。大きく分けて5種類あります。
・休職開始の診断書
・休職を延長するという趣旨の診断書
・復職許可の診断書
・就業制限の診断書
・病名を告げる診断書
そのなかで、社員が必ず会社に提出しなければならないと言える3つの診断書があります。1つ目は休職が必要だという休職開始の診断書、2つ目は休職を延長するという趣旨の診断書、そして3つ目は復職が可能であるという復職許可の診断書です。
さらに、必要に応じて主治医から会社に提出する必要がある診断書が2つあります。1つは就業制限が必要なときに、その旨を書いた診断書、もう1つは病名を告げる診断書です。
これまで、産業医面談をしていない社員が、会社にいきなり診断書を提出することがありました。特に、病名を告げる(治療中であることを告げる)だけの診断書です。
おそらく、何らかの不満を会社に持っていたり、病気でしんどすぎることを会社(上司)に理解してほしかったり(そして業務負担を減らしてほしいと思って)、切実な気持ちで提出されることが多いのだと思います。
しかし、病名や治療中であることを会社に伝えても何も変わりません。就業上の配慮が必要であれば、そのことを明記してある診断書を提出する必要があります。
そのため、5種類の診断書のうち、病名や治療中であることを伝えるだけの診断書の提出は不要なこともあります。産業医と相談したり、目的を考えたりした上で診断書を提出するようにするといいでしょう。
● 職場で“配慮”や“就業制限”を 求める診断書の注意点
病気のために、職場で何らかの配慮を求めるのであれば、“配慮が必要である、就業制限が必要である”という趣旨の診断書を書いてもらいましょう。
このときに注意してほしいことがあります。主治医の先生は職場や就業規則を知っているわけではない、ということです。
時に、社員の言いなりの就業制限を求める診断書も見ることがあります。たとえば、「週3日の勤務が必要である」「半日勤務」「在宅勤務を」などと記載されている診断書です。実は、会社側は、診断書を読めば、言いなりになって書いているかどうかわかります。
これはとても危険です。