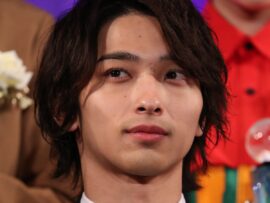近年、日本では大麻による検挙者数が増加傾向にある。
警察庁の統計によると、2024年中に、大麻により検挙された人数は6078人に上り、2015年の2101人から約3倍近く増加している。
大麻に関する議論を巡っては「非犯罪化し、刑事施設外での自主的な治療に専念すべき」といった意見や“合法化”を求める一部の声がある一方、芸能人や有名大学の学生による大麻事件が発生すると“センセーショナル”な報道も目立つ。
本記事では「大麻とは何か」や「日本国内での大麻を取り巻く環境」について、文化社会学と犯罪社会学の観点から大麻について調査・研究をする佛教大学准教授の山本奈生氏が解説。今回は大麻文化や事件を巡る日本の言論の変化について紹介する。(第4回/全6回)
※ この記事は山本奈生氏の書籍『大麻の社会学』(青弓社)より一部抜粋・構成。
「ダメ。ゼッタイ。」以前のサブカル、週刊誌の論調とは…
1970年時点の論調は、特に大衆週刊誌では現在と大いに異なるものだった。まだ「ダメ。ゼッタイ。」キャンペーンを経ておらず、大麻へのバッシングが自明ではなく「奇異なもの」だった往年に、週刊誌は「米国では一般的になっている」「それほど害がない」「大麻のトリップとは一体何か」という興味本位で警察報道から距離をとる言説を採用していたのである。
大宅文庫による関連記事検索では、当時の大麻報道は「平凡パンチ」(平凡出版→マガジンハウス)が一手に複数の記事を書き、連続特集といっていいキャンペーンを展開していたことが明白である。
「これがマリワナの幻想世界だ」「マリワナ・パーティー体験ルポ」などの記事群では、アメリカのヒッピー文化を紹介しながら、国内での擁護意見などを多数紹介している。
たとえば1970年2月16日号「平凡パンチ」の「これがマリワナの幻想世界だ」では、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)の「週刊アンポ」でもマリワナ特集がされていると触れて、なだいなだの「禁止論者は、マリワナと麻薬との区別をほとんど知らない。実際には、マリワナは、麻薬とは全く異なったものだ」という発言、植草甚一や筒井康隆らの相対化された意見を多く取り上げた。
後続の号でも特集を組んで、8月にはニューヨークへの「パーティー体験ルポ」も掲出している。このように紹介された大麻への相対的意見は、まだ1970年代には残存していた。
ジャズ批評の植草甚一が「宝島」(JICC出版局)で特集を組み「マリワナについて陽気に考えよう」(1975年10月号)としたように、サブカル、週刊誌の言説空間にはいまだ「ダメ。ゼッタイ。」の大前提は組み込まれていなかった。