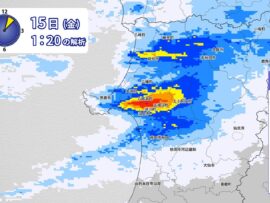目の前の死体は何を伝えたいのか――。元監察医の上野正彦氏は「轢き逃げされたとか絞殺されたとか、突然大変なことを言い出す死体もある……」と語る。現役時代に遭遇した切なく記憶から消えることのない事件・事故の数々。妻を介護する夫は、最後になぜその行動をとったのか。本記事では、上野正彦氏の最新刊『死体はこう言った』(ポプラ社)から内容を一部抜粋・編集して紹介します。
● もう妻の世話を一人で看られない
近所でも評判の仲のよい夫婦がいた。
毎日二人で庭の草木の手入れをし、晴れた日には二人で連れ添って散歩に行く姿が見られた。
近所のスーパーでは、二人で品物を手に取って、楽しそうにじっくりと選んでいる姿がよく目撃されていた。
しかし、五年前に妻が脳梗塞で倒れ、その後遺症で半身不随になった。すでに退職して家にいた夫は、妻のために食事の世話から下の世話まで全て一人で介護をしていたのである。
朝起きたらまず食事を作る。おはしが持てない妻に食べさせ、その後おむつを換える。
妻が寝ているベッドのシーツも毎日換えた。汚れたら衣服を着替えさせ、優しく語りかけながら妻の髪にくしも入れた。
さすがに毎日とはいかなかったが、二日に一回は、お風呂にも入れた。女性とはいっても、妻を支えて持ち上げて運び、お風呂に入れるのは大変だった。
病気になる前は近隣付き合いもあったのに、妻が倒れてからはめっきり外出することもなくなり、夫は姿を見せなくなった。心配した近所の人が家の様子を見に行っても応答はなく、窓も閉め切っており様子が分からない。
この夫婦には子どもがいなかったから、他に頼る人もいなかった。夫は真面目な人だったのであろう。自分一人で妻を看ようと全てを抱え込み、行政に助けを求めることもなかった。
5年間の介護の末、わずかだった貯金も底をつき、彼の疲労も限界に達した。
検死現場に行ったら、歩けるスペースがないくらい家の中が散らかっていた。
日々の妻の世話に必死で、家を掃除するという気力もなかった。この5年間で夫は、顔色も悪くなり痩せ細っていった。もう自分一人では妻は看られない。
限界だ。ここで私が倒れたら誰が妻を介護してくれるのだろうか。妻をおいて自分が先に死ぬことはできない。
妻が先に死んだら、自分は楽になるかもしれない。いっそのこと妻を殺してしまおうか。でも、そんなことはできない。
夫は毎晩苦しんだ。悪夢を見るようになり、うなされた。眠れなくなった。
そして苦しみ抜いた結果、夫は、妻を殺して自分も死のうと心中を決意した。
● 「自分が妻を殺しました」
妻は浴槽の中で溺没の状態で見つかった。
夫は睡眠薬を飲んで自殺をはかったが、たまたま心配して様子を見に来た近所の人に発見されて一命を取り留めた。
意識を取り戻した夫は、警官に妻のことを聞かれた。夫は病室のベッドで窓の遠くを見ながら、「自分が妻を殺しました」と静かに、はっきりとした口調で自白した。
しかし、妻を検死してみると、その痩せ細った手首に、夫の手の跡がくっきりと残っていたのである。
それは妻を殺そうと溺れさせるために押さえつけた跡ではなく、むしろ引っ張り上げたときにできる手の形の跡だと分かった。