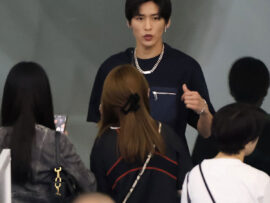(CNN) 長時間勤務が続くと脳の構造が変化して、認知機能や感情制御に影響を及ぼす恐れがあるという研究結果が、13日の医学誌に発表された。働き過ぎると身体的、精神的な無理が重なり、休養不足も加わって脳に「重大な変化」が起きると指摘している。
この研究は韓国の中央大学と延世大学の研究者が実施。医療従事者110人を「働き過ぎ」と「働き過ぎではない」グループに分け、脳の状態を比較した。
韓国では週の労働時間は52時間が上限とされており、働き過ぎは公衆衛生問題となっている。
週52時間以上の勤務で「働き過ぎ」に分類された32人は、そうでないグループに比べて平均年齢が若くて就業年数が短く、教育水準は高かった。
研究チームはそれぞれのグループについてMRIの診断画像などを使って脳の容積を分析。脳内のさまざまな領域で灰白質の違いを特定し、脳の構造を比較した。
その結果、「週52時間以上働いた人は、標準時間内労働の人と違って、実行機能と感情制御に関連する脳の領域に著しい変化が見られた」と発表している。
脳の中でも認知力や注意力、記憶力、言語処理などにかかわる中前頭回や、感情処理や自己認識、社会的状況認識にかかわる島皮質などの領域は、容積が増えていることが分かった。
この結果について研究者は、仕事量の増加と脳のそうした領域の変化との「潜在的関係」をうかがわせると指摘。働き過ぎの人々が訴える認知力の問題や感情問題の生物学的根拠を提示していると解説する。
論文を発表した延世大学の研究者はCNNの取材に対し、こうした変化は環境ストレスがなくなれば「少なくとも部分的には」元に戻るかもしれないと予想。それでも脳が標準的な状態に戻るためにははるかに長い時間がかかるだろうと話している。
長時間労働が健康に及ぼす悪影響については過去の研究でも指摘されている。国際労働機関(ILO)と世界保健機関(WHO)の2021年の調査によると、働き過ぎで死亡する人は推定で年間74万5000人以上。長時間労働は女性の糖尿病リスク増大や認知能力の低下にもつながることが分かっている。
ただ、働き過ぎが行動や心に与えるそうした影響については知られていても、その原因となる神経のメカニズムや解剖学的変化についてはこれまでよく分かっていなかった。
21年のILOとWHOの調査を率いた専門家は今回の研究について、長時間労働が健康に与える「根本的な影響」の解明につながる「重要な新証拠」になると評価している。