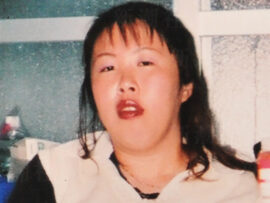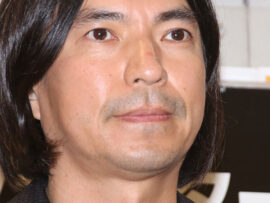日本の夏が深まるこの季節、全国を覆い尽くすのが、いわゆる「8月ジャーナリズム」です。毎年8月6日の「広島原爆の日」から15日の「終戦記念日」にかけて、新聞やテレビなどのメディアは「第2次世界大戦」に関連する特集を次々と展開します。現在50代前半の筆者は、80年前の8月を知りませんが、四半世紀以上にわたる自衛官生活と大学院での政軍関係研究を通じて、軍事に関する専門知識を培ってきました。そのような筆者にとって、この「8月ジャーナリズム」には、しばしば違和感を感じることがあります。それは、筆者自身のイデオロギーとは異なる、「当時、当たり前だったこと」が現代では忘れ去られていることに起因する「ズレ」です。本稿では、筆者が解説を担当したオーラルヒストリー集、和久井香菜子氏の著書『私たちもみんな子どもだった 戦争が日常だった私たちの体験記』(2021年、ハガツサブックス刊)を振り返りながら、歴史と現在の関係性について考察します。
 歴史を記録する手とペン。戦時中の日常やオーラルヒストリーの重要性を想起させる。
歴史を記録する手とペン。戦時中の日常やオーラルヒストリーの重要性を想起させる。
忘れ去られた「当時の当たり前」と歴史認識の乖離
平成から令和へと時代が移り変わる中、筆者はライターの和久井香菜子氏と出会いました。彼女は、終戦当時子どもだった人々が、どこで、どのように「玉音放送」を聞いたのかという「戦争体験」を「オーラルヒストリー」として収集していました。筆者は、その軍事面での考証や解説を担当することになったのです。
筆者と同世代の和久井氏は、「戦争を経験した世代と、私たちのように経験していない世代とでは、これほどまでに感覚が違うのか」と驚きを口にしました。「戦後教育」を受けた彼女は、戦争を生きた世代は皆一様に「被害者」であり「犠牲者」であると教えられてきました。しかし、実際に人々の話を聞いてみると、「誰一人として同じ体験はしておらず、一人ひとりのエピソードが生き生きとしていた」ことに気づいたと言います。
戦争体験の多層性と「当たり前」の再評価
この「誰一人として同じ体験はしていない」という事実は、本来「当たり前の話」であるはずです。しかし、この「当たり前」の多様な物語が、これまでの歴史の網からすくい取られず、抜け落ちてしまっているのです。筆者が「8月ジャーナリズム」に感じる「ズレ」は、まさにこの点にあります。私たちは、それぞれの「当時の当たり前」を多様な形でそのまま受け止めることこそが、より多角的で真実味のある「歴史認識」へと繋がると考え、その重要性を強く認識しています。