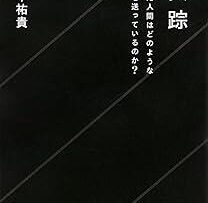2023年、全国の山で発生した遭難は3126件、遭難者は3568人で、統計が残る1961年以降の最多を更新した。遭難の増加は携帯電話の有効エリアが年々広がり、かつては自己解決していた事例での通報が増えたことなども大きく、必ずしも重大事故の増加を意味しない。それでも、23年は335人が死亡、または行方不明になっている。
【写真】遭難者を生存発見し救助する山岳遭難捜索ネットワークメンバーの写真はこちら
遭難の増加を背景に、登山中の事故などに備える山岳保険の重要性が紹介される機会も増えてきた。中でも見逃せないのが遭難時の捜索や救助費用を補償するものだ。
しかし、登山向けとして売り出されている保険ならばどれでも安心……では実はない、という。
* * *
捜索・救助は警察や消防が担うのが基本で、本人や家族には一部の例外を除き費用請求されない。ただ、公的機関の捜索は短いと数日、多くは1週間程度で終了する。その間に見つからなければ民間団体などに依頼することになる。警察や消防の捜索が続いている間でも救助の可能性を高めるために民間に出動を依頼するケースもあるし、山小屋スタッフなどが駆け付けることもある。これら民間人の活動には1人1日数万円の費用がかかる。
■生命保険受け取れない
山岳ガイドで、民間の捜索・救助チーム「山岳遭難捜索ネットワーク」を率いる三笘育さんは言う。
「私たちの場合、出動隊員の人件費は1人1日5万円。入山口やある程度の目的地がわかるケースでは10人日(人数×日数)くらいで見つかることが多いので、諸経費も含めて100万円弱のイメージでしょうか。ただ、どうしても見つからずに捜索を継続し、数百万円の請求になってしまうこともあります。自分のためなのはもちろん、家族のためにも遭難捜索・救助に備える保険は必要だと思います」
金銭面だけを考えると、遭難者の家族が最も困るのは「行方不明になって見つからない」ことだ。行方不明者を死とみなすには失踪宣告を申し立てて認められる必要があるが、申し立てができるのは「死亡の原因となる危難に遭遇」したと認められる危難失踪で遭難から1年、一般的な行方不明と同じ普通失踪なら7年が経過してから。三笘さんは続ける。
「家族はその間生命保険を受け取れず、住宅ローンなどの支払いも免除されず、逆に年金などは停止されます。捜索を続けるとどうしても高額になるし、捜索をやめることも簡単ではありません」
位置情報を共有できるアプリを使うなど発見されやすくする対策はもちろん、見つからない時に備えた保険も現代の登山には欠かせないのだ。
■民間ヘリはほぼ飛ばない
ただ、遭難捜索・救助については誤解も多い。ひとつがヘリコプターによる救助費用だろう。
上空からの捜索が有効な場合や地上搬送が難しい場合にはヘリコプターが出動する。高山が多い長野県では、2024年に発生した321件の山岳遭難のうち半数超の164件で計201回ヘリコプターが出動し、166人を救助・収容した。遭難とヘリコプターは切り離せない関係なのだ。
そんなヘリコプターをめぐり、「民間ヘリが出動すると、1回数十万円請求される」との説明を頻繁に目にする。ネット上の記事でも無数に確認でき、「ヘリ代が高額だから保険は必須」というロジックで語られることも少なくない。
ただ、実は現在、国内の山岳遭難救助で民間ヘリコプターが飛ぶことは原則ない。かつては山岳救助を事業として担う航空会社があったが、2000年代に撤退した。その後も民間ヘリが搬送等に協力するケースがときおりあったものの、ここ10年ほどはほぼなくなった。
会員向けに民間ヘリをチャーターし、オペレーターが乗り込んで捜索を行うサービスを提供する会社はあるが、発見しても救助はできず、地上部隊や公的機関に位置情報を引き継ぐことになる。
また、行政や警察のヘリコプターは埼玉県の防災ヘリだけが一部山域を対象に有料化されており、5分8千円、1時間のフライトなら9万6千円の手数料がかかるが、それ以外の地域では今のところ利用者へ請求されない。
三笘さんは言う。
「家族が民間会社に頼んで遊覧飛行のように上空を飛ぶことは不可能ではありませんが、警察や消防が動く中では意味がないでしょう。ヘリコプターについては、なぜか20年以上前の情報がアップデートされていません」