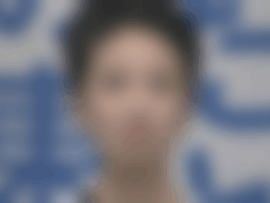[ad_1]
4月6日の兵庫県赤穂市議選で初当選した山谷真慶市議について、赤穂市選挙管理委員会は同月17日に、「市内に居住実態がない」とする当選無効を求める異議申し立てがあったと発表した。
【本人X投稿】「私は居住要件を満たしていると認識しております」
山谷氏は「躍動の会」の公認候補として赤穂市議会議員選挙に立候補し、20人中15位(定数17)で当選した。躍動の会は、兵庫県の斎藤元彦知事に対する告発文をめぐり、真偽不明の情報や百条委員会の非公開音声データを外部の政治団体代表に提供したなどの不祥事を理由とし、「兵庫維新の会」から除名・離党勧告の処分を受けた県議3名が3月に設立した会派である。
市区町村議会議員、都道府県議会議員に立候補する資格として、3か月以上その自治体に居住することが求められている(公職選挙法9条2項、3項参照)。居住要件の解釈およびそれに関する問題について、「議員法務」の第一人者で、東京都国分寺市議会議員を3期10年にわたり務めた経歴がある三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に聞いた。
居住実態に関する“疑惑”が持ち上がる背景
昨今、地方議会議員選挙ではしばしば、選挙結果を受けて「居住要件」についての疑惑が持ち上がる。なぜなのか。三葛弁護士は2つの要因を挙げる。
三葛弁護士:「第一に、地方議会選挙に立候補する方が必ずしも地域に密着した方ばかりではなくなってきているという実態です。
近年は、落選したら別の自治体で挑戦するという、複数の自治体で立候補する人が増えています。そのような経歴がある候補者については、居住要件を疑われやすいといえます。
第二に、立候補届け出という短い期間に、各候補者の居住実態について審査するのは困難であり、非現実的ということが挙げられます。
そのため、立候補届け出の際に最低限、その自治体に住民票があるという『形式要件』をみたしているかを判断するほかありません。実態については、問題がある場合に事後的に詳しく調査して判断せざるを得ないのです」
居住実態の判断基準は「不明確」だが…
そもそも居住実態とはどのようなものか。三葛弁護士は、実務上も学説上も、居住実態についての厳密な判断基準は必ずしも明らかにはされていないと説明する。
三葛弁護士:「最近の裁判例によると、公職選挙法上の『住所』とは、『⽣活の本拠、すなわち、その者の⽣活に最も関係の深い⼀般的⽣活、全⽣活の中⼼を指すものであり、⼀定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に⽣活の本拠といえる実体を具備しているか否かにより決すべきもの』とされています(東京高裁令和3年(2021年)12月23日判決、最高裁令和4年(2022年)5月17日決定)。
ただし、『客観的に生活の本拠と言える実体』などの数量的な基準を厳密に設けることは適切ではなく、現実的でもありません。たとえば、
・朝早くから夜遅くまで勤務先におり、勤務先に寝泊まりすることも多い場合
・マイホームに家族を残して単身赴任し、休暇に帰ってくる場合
・長距離ドライバーで長期間家を空ける場合
・遠洋漁業従事者で年数日しか帰ってこない場合
などは、住民票を動かしようがありません。にもかかわらず『居住実態』を否定し、地元の地方議会議員選挙に立候補できないとなれば、事実上、被選挙権(憲法15条参照)の侵害にあたる可能性があります」
実際、過去に上記のような事例について居住要件が問題となったことは、「聞いたことがない」とする。
三葛弁護士:「たとえば、離島選出の議員や、議会までかなりの距離がある議員(北海道等)などが、議会中選挙区を離れ議会のそばに長く滞在していても、居住要件について誰も問題にしません」
[ad_2]
Source link