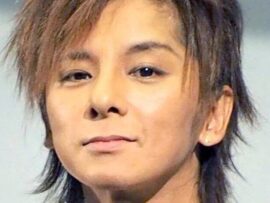千年に一回起こるかどうかという、非常にまれな東日本大震災。人々の中には、「大きな地震があったから、当分同規模な地震はこないだろう」と楽観視する人も。しかしその考えが間違っている理由とは…? 京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏の新刊『 「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室 』(ダイヤモンド社)より一部抜粋してお届けする。(全3回の1回目/ つづき を読む)
◆◆◆
「当分、大規模地震はこない」は間違った考え
東日本大震災は千年に一回起こるかどうかという、非常にまれな、日本の地震観測史上最大規模の大地震でした。しかもマグニチュード(M)9.0という大きな本震のあとに、余震としてM7クラスやM6以上の巨大な余震が何度も起こっています。
よく、「東日本大震災の地震で大きなエネルギーが解放されたので、もうエネルギーは残っていない。したがって当分は地震がこないのではないか」という質問を受けます。
これはとんでもない間違いで、プレートにたまったエネルギーは、これからも震源域をどんどん広げながら解放される可能性が高くなっています。
東日本大震災は、北米プレートに乗っている東日本の地盤のひずみ状態を変えてしまいました。ですから、東日本大震災以降、地震発生の形態がかなり変わってしまったのです。日本列島の内陸部でも、2000以上ある活断層が活発に動き出す懸念が生じています。
なぜ地震で津波が起きるのか
地震を考える際に欠かせないのがプレート・テクトニクスです。これまでにお話しした部分もありますが、おさらいも兼ねて、その話からはじめましょう。
日本列島は4つのプレートが取り囲んでいます。海洋プレートが2つ、大陸プレートが2つです。海洋プレートは太平洋プレートとフィリピン海プレートで、大陸プレートは北米プレートとユーラシアプレートです。これらの4つのプレートがひしめき合っていて、「変動帯」となっています。変動帯とは地殻変動などが激しくて活発な帯状の地帯のことです。
ウェゲナーが最初に「大陸は移動する」というアイデアを出して、それが実証されてプレート・テクトニクスになりました。地球上の表面は10枚ほどのプレートがあって、それが水平に動くということです。水平に動いたプレートはどうなるかというと日本列島でぶつかって片方が斜め下に沈み込むんです。
この図は日本列島の地中の様子です。
日本列島が乗っているところで、海洋プレートが年間に8〜10センチメートルの速度で沈み込んでいます。大陸プレートはそれに応じて引きずられる。どんどん引きずられていくんですが、あるところで限界に達すると跳ね返ります。これがプレートを原因とする大きな地震の仕組みです。
ボンと跳ね返るのですが、海のなかの話だから、海底が隆起することになる。すると、その海底の上の海水は高さ30メートルぐらい持ち上げられ、行き場を求めて左右(東西)に動くんです。左(西)側に動くと日本列島があるので津波になります。
死者数32万人の可能性…「南海トラフ地震」が東日本大震災よりも恐ろしい理由 へ続く
鎌田 浩毅/Webオリジナル(外部転載)