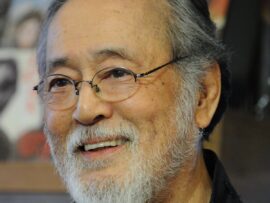中学3年生を対象とした全国学力テストで、1983年には約7割が正解していたある数学の問題。だが2012年には、正答率が2割近くも下がっていた。いったい何が起きたのか――。東京理科大学理学部教授や桜美林大学リベラルアーツ学群教授を歴任し、数学教育に半世紀以上携わってきた芳沢光雄氏が、現在の学びの現場に感じている「異変」とその対策を考える。
【実際の回答を再現】厳しすぎ?意地悪?漢字テストで”不正解”になった「男」「加」「口」
***
筆者は専任教員として5つの大学、非常勤講師として5つの大学に勤務し、定年退職となった一昨年の3月末まで45年間に亘ってのべ1万5000人の学生に授業をしてきた(文系・理系ほぼ半々)。また90年代半ばから、小・中・高校合わせて1万5000人を対象として出前授業も行ってきた。
その長い年月を振り返ると、指摘しなくてはならない大きな変化を感じることがある。それは「試行錯誤」の問題に取り組む学生の姿である。昔は、時間が余った授業中に誰でもチャレンジできる試行錯誤の問題を出すと、全員が楽しく取り組む姿をよく見たものである。
「この問題の“やり方”を教えてください」
たとえば、「外見同一の玉が13個あって、そのうち1個だけ重さが違う(他と比べて軽いか重いかは不明)。天秤を3回使ってそれを見付ける方法を述べよ」というような易しくない問題である(この問題は拙著『離散数学入門』で述べたように一般化できる)。そして、あまり多くの時間を使うのも如何なものかと思って解法を述べようとすると、「先生、いま考えているから、答えは言わないでください」と怒られたことが何度もあった。それが近年になると、そのような試行錯誤の問題を出すと、直ぐに「この問題の“やり方”を教えてください」という質問がしばしば寄せられたのである。しかも、そのような質問をする学生は真面目で、「やり方」を真似して解くような微分積分の計算問題などは得意である。
ある日、偶然にもそのような質問をしたことがある学生が訪ねてきて、授業ノートを示しながら「今日の授業で試験対策として暗記しておくべきことはどこですか」という質問をしてきた。不思議に思っていろいろ尋ねると、「数学の学びとはやり方の暗記」だけだと思っていたのだ。筆者は学生からの授業感想文は大学を離れても大切に保管してあり、「問題解法の暗記より定理や公式の証明を大切にして、いろいろ考えることを大切にした授業を受けたのは忘れられない」という内容のものが相当多くあることを踏まえると、筆者の驚きが分かってもらえると思う。
同じ傾向は、数学の入学試験の監督をしてきたことからも感じた。昔は記述式試験が中心であったこともあるが、ほぼ全員が終了時間ギリギリまで真剣に答案に向かっていた姿が今も目に浮かぶ。それが近年は、大学入試センター試験のようなマークシート式試験が中心になった影響か、「やり方」を暗記した問題は直ぐに処理して、「やり方」を思い出せない問題は考えることなく飛ばしてしまう姿を多く見るようになった。そして、諦めの早い受験生は机の上で静かに寝てしまう。まるで暗記科目の試験監督をしているような思いをしたのである。