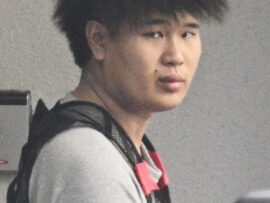〈「欠点は俺に惚れないことだ」出会った当時は16歳…美輪明宏が語る、三島由紀夫が自決の1週間前に持ってきた“100本のバラ”に隠された意味とは〉 から続く
【画像】タキシードに身を包んで妻の隣で…自決の12年前、国際文化会館で行った三島由紀夫の結婚披露宴の写真を見る
今年1月14日に生誕100周年を迎えた三島由紀夫。1925年に生まれ、多感な10代の時期を戦時下で過ごした。20代の三島は戦後復興の中で次々と作品を発表し、30代で高度経済成長期を経験する。そして――。
45歳で割腹自殺した三島。その最期の10数年について、 『21世紀のための三島由紀夫入門』 (新潮社)から抜粋してお届けする。「昭和」と共に駆け抜けた三島の人生、その死が問いかけるものとは。(全3回の2回目/ 続きを読む )
解説=井上隆史
◆◆◆
肉体を鍛え、高みを目指したが…
病弱な幼少期を過ごし、自身の身体にコンプレックスを抱いていた三島は、昭和30年にボディビルを始めます。以後、ボクシング、剣道などを通して自分の身体を鍛えてゆく。
昭和31年は出版社系では初の週刊誌「週刊新潮」が創刊された年ですが、従来の作家像を裏切る三島のふるまいは、文芸誌のみならず、週刊誌・婦人誌などにも取り上げられ、世間の耳目を集めました。しかし、戦後社会を否定しようとする自分が、その戦後社会の寵児となるとは、何事であろう。三島のなかで、次第に微妙なバランスが崩れ始めます。
『近代能楽集』を翻訳出版していたニューヨークのクノップ社に招かれての渡米では、予定されていた同作の上演が頓挫し、残念な思いを抱いての帰国。「金閣寺」では個人を描いたから今度は社会を描くと、昭和33年3月から「鏡子の家」の執筆に取りかかるのですが、戦後社会を蝕む欺瞞と虚無を描いたこの野心作は、読者の共感を得られませんでした。
「金閣寺」のころには、戦後復興に無意識の違和感を抱いていた読者も、高度経済成長の波に乗って奔走することに明け暮れ、「鏡子の家」に込められた三島の叫びを聞き取ることができなくなっていました。また、「鏡子の家」に対する批判に、登場人物が作者の分身にすぎないというものがあります。なるほど画家の夏雄には作家三島が、拳闘選手の峻吉にはボクシングの経験が投影されています。大手商社の副社長の娘と結婚する清一郎のモデルもまた三島その人。
三島は昭和33年6月に、日本画家・杉山寧(やすし)の娘・瑤子(ようこ)と、明治記念館で華燭の典を挙げました。媒酌人は川端康成夫妻です。3月に母親の末期癌が疑われ(後日、悪性腫瘍ではないことが判明しますが)、早く安心させたかったため結婚を急いだという説があり、ニューヨークで「来年はきっと結婚するぞ」と語っていたともいいます。結婚の翌年には新居を建て、長女も生まれます。どんな家庭生活にも欺瞞はありますが、いわゆる“普通の結婚生活”を始めた作家にとって、現実社会のあらゆる欺瞞をも引き受けようとすることが、誠意の証だったのかもしれません。