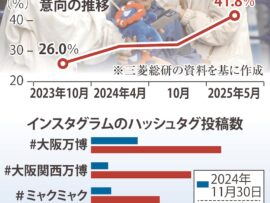「日本の学術の“終わりの始まり”になるのでは――」。ノーベル物理学賞受賞者で日本学術会議の前会長、梶田隆章・東京大卓越教授が今年2月に記者会見で述べたこの懸念が、今、現実味を帯びつつある。日本学術会議を国の特別機関から特殊法人へと改編する法案の審議が、参議院で大詰めを迎えているためだ。
法案審議の現状と広がる反対運動
近日中にも所管の内閣委員会で強行採決されるかもしれないという緊迫した状況の中、国会前では連日のように、法案に反対する学者や市民による座り込みや集会が行われている。
梶田氏をはじめ、学術会議の歴代会長6人は国会に法案の廃案を求める声明を出している。学術会議自身も4月の総会で修正を求める決議を行った。さらに、多くの学会や学協会から法案の廃案や修正を求める声明が続々と発表されており、その数は5月末までに100を超えた。
市民からも約6万8000筆のオンライン署名が集まるなど、広範な反対の声が上がっている。しかし、内閣府は最近集まった約4万2000筆について、職員の多忙を理由に面会での受け取りを拒否したとされる。
 参議院議員会館前で日本学術会議法人化法案の廃案を求める学者たちの座り込みの様子(隠岐さや香、加藤陽子、小澤隆一、田中優子氏ら)
参議院議員会館前で日本学術会議法人化法案の廃案を求める学者たちの座り込みの様子(隠岐さや香、加藤陽子、小澤隆一、田中優子氏ら)
法案に潜む深刻な問題点
この法案の内容や提出までの経緯には、極めて深刻かつ多くの問題点が指摘されている。特に、会員選考や日々の活動に政府がさまざまな形で関与できる仕組みが盛り込まれている点が批判の的となっている。
現行の法案による法人化が実現すれば、ナショナルアカデミーとしての機能は強まるどころか、むしろ弱体化していく可能性が高い。日本の科学研究や科学技術政策の観点からも、強い危機感が抱かれている。
会員選考への政府関与の仕組み
ナショナルアカデミーは国の科学者コミュニティを代表して政策提言を行う学術団体であり、日本では日本学術会議がその役割を担う。自然科学から人文・社会科学まで幅広い分野の会員が議論を重ね、科学的助言を政府や社会に提供している。
現在の学術会議は政府から独立した国の特別機関だが、法案では国から独立した特殊法人として再編される。ここで最も問題視されているのが、会員の選考プロセスへの新たな介入の仕組みである。
現在は現会員が次の会員候補者を推薦する「コ・オプテーション」方式を採用しており、これは多くの国のナショナルアカデミーで標準的な方法とされている。
しかし、法案では、2026年10月の新法人発足時とその3年後には、特別に設置された選考委員会が候補者を選ぶとされている。この委員会のメンバーは、会長が首相の指定する学識経験者と協議して決めなければならない。
その後は会員で構成された委員会が候補者を選ぶ形となるが、その際には会員以外で構成される「選定助言委員会」に意見を聞くことが半ば義務付けられる仕組みだ。
活動への管理強化
会員選考に加え、学術会議の日々の活動に関しても、外部からの管理を強化する仕組みが法案には盛り込まれている。
新法人には、いずれも会員以外で構成される「運営助言委員会」、「監事」、「評価委員会」が新たに設置される予定だ。特に、監事と評価委員会のメンバーは首相が任命することになっている。
これらの複数の管理システムが張り巡らされることにより、新法人が現在のような独立性や自律性を保つことは困難になるだろうと懸念されている。
まとめ
このように、日本学術会議の法人化法案は、その会員選考や活動に対する政府の関与を強める内容となっており、学術会議が持つナショナルアカデミーとしての独立性と自律性を大きく損なうとの指摘が相次いでいる。
法案がこのまま成立すれば、日本の学術が培ってきた自由な研究環境や政府への科学的助言機能が弱体化し、“終わりの始まり”となるのではないかという強い危機感が専門家や関係者の間で広がっている。