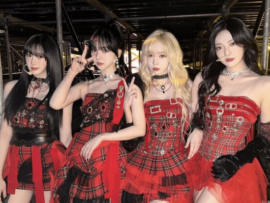今春4月から、沖縄県産のゴーヤーやフルーツなどの島外持ち出しに制限がかかっている。その背景にあるのは、恐るべき外来特殊害虫「セグロウリミバエ」の発生だ。農作物に甚大な被害をもたらす「8ミリの悪魔」の脅威が、沖縄本島全体に広がりつつあり、一刻の猶予も許されない状況となっている。
セグロウリミバエ、その発生と被害
事の発端は、2024年3月14日。農作物への害虫侵入を監視するトラップが、沖縄本島名護市で1匹のハエを捕獲したことから始まる。
 沖縄県名護市のトラップで捕獲された外来特殊害虫セグロウリミバエ成虫(2024年3月14日)
沖縄県名護市のトラップで捕獲された外来特殊害虫セグロウリミバエ成虫(2024年3月14日)
このハエが専門家の調査により、幼虫がウリ類、ナス類、さらにはパパイヤなどの熱帯果樹の果肉を食い荒らし、壊滅的な被害を引き起こすセグロウリミバエ(学名: Bactrocera tau)であることが判明した。海外では深刻な農業被害が報告されている危険な外来種である。
セグロウリミバエの生態と日本での過去
セグロウリミバエのメス成虫は、生果実に産卵する。約1日で孵化した幼虫は果肉内で約14日間成長し、その後果実から飛び降りて地中へ潜り、蛹となる。約8日後に羽化して再び地上に現れ、繁殖を繰り返す。この幼虫による食害が、農産物の商品価値を完全に失わせてしまう。

日本国内では、過去に1998年と2003年に石垣島で少数確認されたのみで、農作物被害の報告はなく自然に終息した。その後21年間、その姿は日本から消えていた。
再び現れた「悪魔」、沖縄本島での現状
しかし、2024年の再発見以来、セグロウリミバエは沖縄本島内で急速に分布を拡大している。進化生物学者の宮竹貴久氏は、害虫防除の最前線での経験から、「外来特殊害虫であるセグロウリミバエの発生は深刻であり、すでに沖縄本島全域に広がりつつある。この事態は一刻の猶予も許されない局面にある」と強い危機感を示している。今回の持ち出し制限は、この緊急事態に対応するための措置なのだ。
セグロウリミバエの再来は、沖縄の農業、特にウリ類やフルーツ農家にとって壊滅的な打撃となりかねない。島外への移動制限は、さらなる分布拡大を防ぐための重要な防御線である。この見えない脅威に対し、正確な情報共有と迅速な対応が求められている。