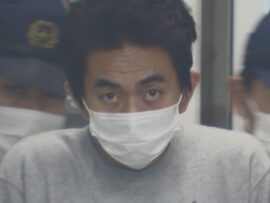2025年7月3日に公示される参議院選挙(7月20日投開票)を前に、主要各紙は6月30日、参院選に関する最新の世論調査結果を一斉に報じました。今回の選挙における主要な争点の一つである消費税減税に対する国民の支持率に注目が集まっています。各紙の調査結果を比較すると、消費税減税への支持割合に大きなばらつきが見られます。産経新聞では70.0%、毎日新聞では55%、読売新聞では50%、そして日本経済新聞では36%という結果でした。このように新聞社によって支持率に差が生じる背景には、調査における質問の仕方の違いが大きく影響しています。
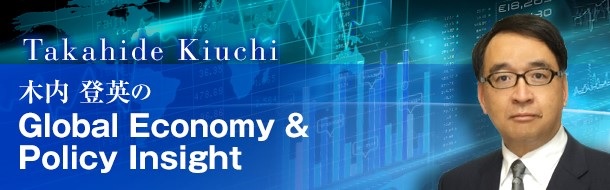 主要各紙による参院選前の消費税減税に関する世論調査結果の比較と質問内容
主要各紙による参院選前の消費税減税に関する世論調査結果の比較と質問内容
具体的に各紙の質問内容を見てみましょう。産経新聞は「物価高対策として現金給与と消費税減税のどちらが望ましいか?」と尋ね、毎日新聞は「給付金案と消費税案のどちらがいいと思いますか?」という設問でした。これに対し、読売新聞は「消費税は、社会保障の財源に充てるよう法律で定められています。消費税の税率を維持する方がよいと思いますか、それとも、引き下げる方が良いと思いますか?」と社会保障との関連を示唆しました。日本経済新聞に至っては、「消費税率を、社会保障の財源を確保するために維持するべきか、赤字国債を発行してでも下げるべきか?」と、財源問題と赤字国債発行のリスクに触れています。
過去の様々な調査でも同様の傾向が見られますが、単に消費税減税に賛成か反対かを問う場合や、今回の産経新聞や毎日新聞のように、直接的な家計支援策(現金給与や給付金)と比較する形で質問を投げかけると、消費税減税を支持する回答割合は高くなる傾向があります。一方で、読売新聞や日本経済新聞のように、消費税が社会保障の重要な財源であることや、安易な減税が将来的な赤字国債の発行につながり得るという消費税減税実施に伴う課題や影響を質問文中に含ませたり示唆したりすると、支持率はより低くなる傾向が見られます。
このような世論調査における質問の仕方が結果を大きく左右するという事実は、メディアの調査手法に関する課題を浮き彫りにするだけでなく、選挙における政策論争のあり方についても重要な問題を提起していると言えるでしょう。単純に「消費税減税が良いか」や「給付金と消費税減税のどちらが良いか」という問いに対しては、目先の家計が楽になる消費税減税を支持するという回答が多くなるのは、ある意味自然なことです。有権者は自身にとって直接的なメリットがある選択肢に惹かれやすい傾向があります。
しかし、消費税減税は単なる税率引き下げにとどまらず、社会全体に様々な波及効果を生じさせます。例えば、物価高対策として消費税を減税した場合、これはすべての消費者が負担する税であるため、富裕層から低所得層まで恩恵が及びます。しかし、それでは物価高で特に大きな打撃を受けている低所得層を集中的に支援するという社会政策的な目的は薄れてしまいます。これに対し、給付金であれば、対象を真に支援が必要な低所得層に絞ることが可能です。また、消費税減税を財源の明確な確保なしに行った場合、それは赤字国債の発行増加、ひいては将来の政府債務の拡大を招きます。この増大した政府債務は、最終的には将来世代、特にその時点での低所得層を含む国民全体に負担としてのしかかる可能性があります。
消費税は、日本の社会保障費を支えるための基礎的な財源と位置づけられています。これは特定の支出にのみ使われる「目的税」ではありませんが、広く国民から安定的に集めることで、高齢化が進む社会で増大する社会保障費を賄う狙いがあります。もし消費税減税を赤字国債で穴埋めする形で行えば、その分の政府債務増加は、将来的には主に所得税収などで賄われる可能性も考えられます。そうなると、社会保障費の負担が現役世代に偏る形となりかねません。本来、消費税が基礎的財源とされたのは、社会保障費の負担を現役世代だけでなく、幅広い世代で分かち合うことを目指したからです。消費税を減税すれば、確かに現世代の可処分所得は一時的に増えるかもしれません。しかし、その裏で政府債務が増加し、遠い将来において、より大きな負担を将来世代に押し付けることになる可能性が高いのです。
このように、消費税減税は単に「税金が安くなる」というだけでなく、社会保障制度の持続可能性、世代間の負担、所得再分配のあり方など、複雑な問題と密接に関わっています。世論調査の質問の仕方一つで支持率が大きく変わることは、有権者が政策の多角的な側面や長期的な影響をどこまで理解した上で判断を下しているのか、そしてメディアや政治がその理解を促す責任をどのように果たしているのか、という根源的な問いを投げかけていると言えるでしょう。今回の参院選における消費税減税を巡る議論は、政策の「見せ方」と「本質」をどう伝えるか、という課題を浮き彫りにしています。