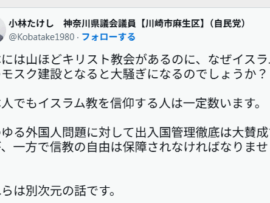「2000万円のコンバイン、普通買えますか?」「どう考えたって経済的にペイしない」――。小泉進次郎農林水産大臣による農業機械リースに関する発言が、再び「思いつきでは」と業界内外から冷ややかな声を集めている。コメ改革でも自民党の支持率上昇に貢献していると見られる小泉大臣だが、農家たちはこの発言をどのように受け止めているのか。複数の農家の本音を探った。
波紋を呼んだ大臣発言は、6月17日の出来事だった。この日、小泉大臣は経団連の筒井義信会長らと会談し、企業の農業参入促進などについて意見交換を行った。会談後の記者会見で飛び出したのが、「農機をリースでまかなわないのはおかしい」といった趣旨の発言だったと全国紙記者は報じている。
小泉大臣の実際の発言は以下の通りだ。「『高い』と言われる農業機械だけども、むしろ例えばコンバインが今、2000万円で。米農家さんは2000万円のコンバインを1年のうち1カ月しか使わないんですよね。だとしたら普通、買えますか? と。むしろそれだったら、買うんではなくてレンタルやリース、こういったことがサービスとして当たり前の農業界に変えていかなきゃいけないんです」。
さらに、建設業界を引き合いに出し、「今、建設業界を見ると、重機や建機のレンタルやリースって当たり前ですよね。どこの中小企業の建設業界の皆さんが、例えばある一つの事業や案件にしか使わない数千万、数億の機械を全部持ってるかといったら、そんな形になってないわけで。農業機械も本来であれば、個人個人で持っていたら、どう考えたって経済的にペイしないのに買ってしまってる。そして売ってる。私はこういったことも変えなきゃいけないと思ってるんです」と持論を展開した。まるで長年の「悪しき体質」を改革する必要があると力強く述べたのである。
 田んぼで稲の生育状況を見る小泉進次郎農林水産大臣。農業機械リースに関する発言が農家の間で波紋を広げている様子。
田んぼで稲の生育状況を見る小泉進次郎農林水産大臣。農業機械リースに関する発言が農家の間で波紋を広げている様子。
農家の現実と乖離した点
しかし、この発言は現場の農家から相次いで疑問視されている。あるベテラン専業農家は「ピンとこないというか、実態が分かっていないなと思いますよね」と率直な感想を述べた。
収穫期の集中と機械共有の難しさ
多くの農家が指摘するのは、コンバインなどの主要農機具は、秋の稲刈りなど「使いたい時がみんな一緒」であるという点だ。これまでにも農家仲間内で機械を共有する案が出たことはあるが、使用時期が重なるため、結局現実的にはうまくいかないという。
この専業農家は続ける。「例えば稲を刈るのが9月の農家と10月の農家があるのなら、そこでコンバインをシェアすればいいという考え方なのかもしれませんが、2000万円クラスのコンバインが必要な大規模農家の場合、稲刈りが1カ月で終わらないところも多いです。さらに、大型の農機を掃除するのも大変な上、自走もできないものも多いため、終わったら即座に他の農家に引き継げるものでもない。『9月と10月で交代しましょう』という単純な話ではないんです」。
兼業農家と天候リスクへの懸念
別の50代農家からは、働き方の多様化や天候リスクに関する懸念が示された。
「兼業農家の場合、作業が土日に集中しがちなので、リースの注文も週末に集中しますよね。これは地域内で激しい機械の取り合いになるでしょう」。一方で、自身のような専業農家については、「収穫の時期はコンバインを丸々1カ月以上動かしっ放しということも珍しくありません。近年は兼業農家の撤退が増え、その土地を引き継いだ専業農家が扱う農地が増えてきている事情もあります。ですから収穫期に1台を長期間借り続けるとなると、他の農家さんとシェアするのは現実的ではないなと感じてしまいます」。
さらに、農業は天候に大きく左右されるため、突発的な事態への対応も考慮が必要だ。「たとえば台風予報が出たらどうするか、という問題もあるでしょうか。台風の被害が出る前に急いで収穫しようと皆が思っても、リースできる台数には限りがあります。リースが主流になると、そのような緊急事態に対応できない農家が増える可能性は高いと思います」と、現場感覚に基づいた意見を述べた。
結論
小泉農水大臣の農業機械リース推進論は、経済的な効率性を追求する視点から述べられたものだが、農家の間では、収穫時期の集中、機械共有の現実的な困難さ、作業時間や経営規模の違い、そして天候リスクへの対応といった、農業現場特有の事情から疑問視する声が多く上がっている。大規模な農機具の導入・維持は農家にとって大きな課題である一方、リース化が農業現場の実態に即しているかについては、さらなる議論と検討が必要なようだ。
参照
https://news.yahoo.co.jp/articles/b597f2d14ecd24c05b5d7154c03295bca4492ec7