高松地方裁判所で、公立学校教員の長時間労働問題を巡る重要な判決がありました。これは、教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の下で「仕方ない」とされがちだった労働実態に一石を投じるものです。刑事罰を伴う労働基準法(労基法)違反を認め、県に損害賠償を命じたこの判決は、教員の働き方を見直す契機となり得ますが、その受け止めには注意が必要です。判決の意義と今後の課題を解説します。
高松地裁判決の具体的な内容と給特法の背景
2025年3月25日、高松地裁は、市立中学校の元教諭が香川県を相手取った裁判で、原告の訴えの一部を認めました。判決は、労働者の労働時間を原則1日8時間・週40時間と定める労基法32条や、休憩に関する労基法34条などに違反すると認定し、県に対し5万円の損害賠償支払いを命じました。公立教員の長時間労働は長年の社会問題となっていますが、労基法違反を具体的に認め、損害賠償支払いを命じた点で、この判決は注目されています。
この背景にあるのが、一般の労働者とは異なる公立教員の給与体系や労働時間に関する特例を定めた給特法です。給特法の下では、教員は正規の勤務時間を超えて勤務する場合でも、時間外勤務手当は原則として支給されず、代わりに給料月額の4%が教職調整額として上乗せされます。この制度が、教員の長時間労働を助長している、あるいは少なくとも法的に「許容」しているかのような誤解を生んできました。今回の高松地裁判決は、給特法が存在しても、労基法の労働時間や休憩に関する規定が適用されうることを示した点で、重要な示唆を与えています。
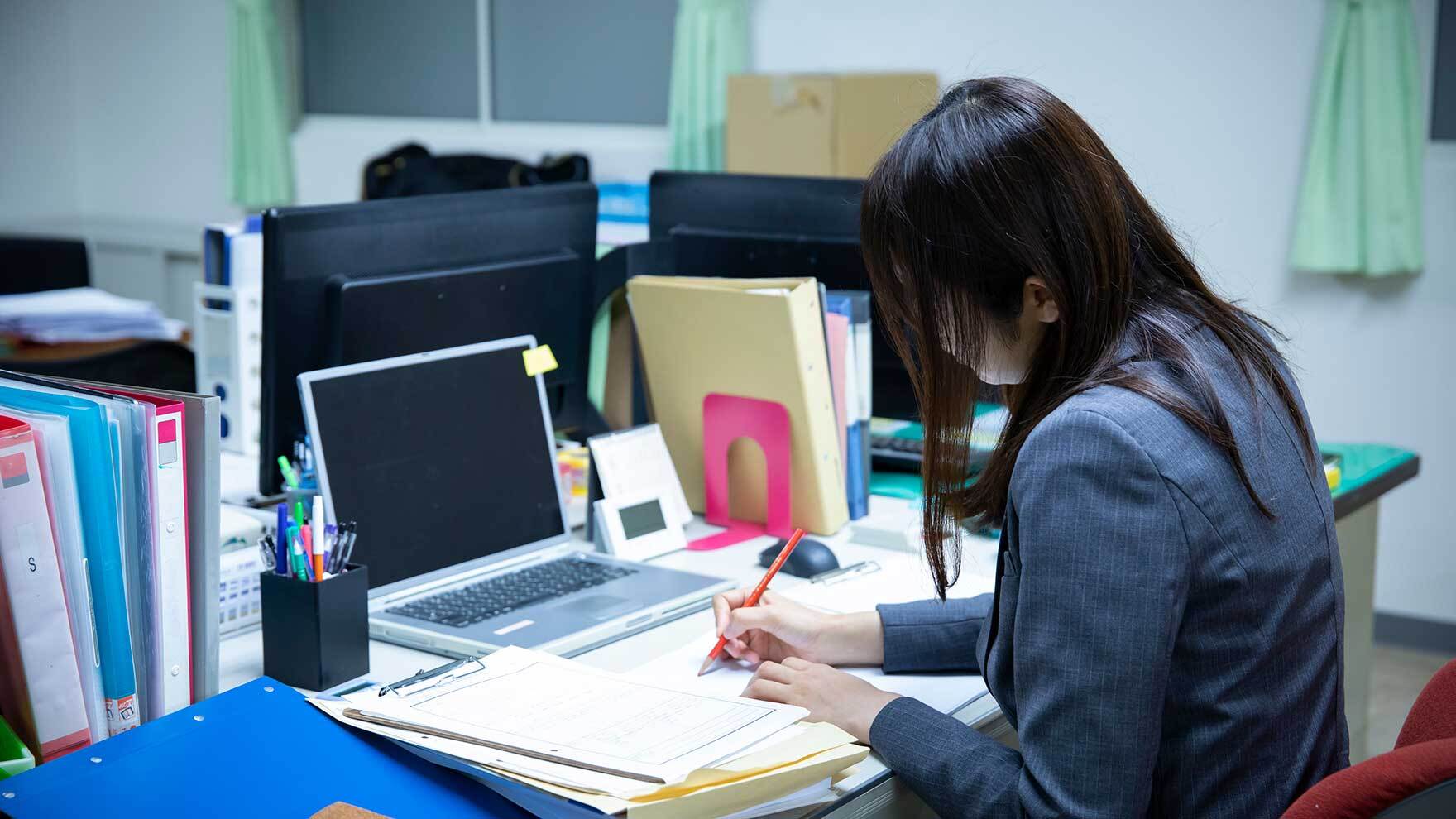 給特法下の教員労働時間について語る弁護士
給特法下の教員労働時間について語る弁護士
判決の限定的な射程と今後の課題
しかしながら、この高松地裁判決の射程(適用範囲)については、慎重な検討が必要です。一部には、公立教員の一般的な長時間労働や休憩が取れない状況について、広く違法性を認めた画期的な判決と受け止める向きもありますが、それは正確ではありません。
今回の判決が違法と認定したのは、原告の通常の勤務時間における残業や休憩取得状況全体についてではありません。判決が焦点を当てたのは、宿泊学習や、それに関連する学年団会議といった、特定の限定的な場面での労働実態のみです。残念ながら、この判決をもって、教員の日常的な長時間勤務が直ちに労基法違反と問える可能性が大きく広がったと結論づけるのは早計と言えるでしょう。
それでも、給特法の下での労働時間管理のあり方に疑問を投げかけ、労基法違反の可能性を示唆したという点では、この判決は意義を持ちます。今後の教員の労働環境改善のためには、給特法の見直しを含め、実効性のある労働時間管理システムの導入や、業務削減など、多角的なアプローチが不可欠です。今回の判決が、長時間労働に苦しむ教員の現状に対する社会的な関心を高め、具体的な改善への議論をさらに加速させるきっかけとなることが期待されます。
結論として、高松地裁判決は公立教員の長時間労働問題、特に給特法の下での労働時間管理に一石を投じる重要な事例です。労基法違反と損害賠償を認めた点は画期的ですが、その判断が限定的な場面に留まったことを理解することが重要です。この判決を起点に、公立教員の適切な労働時間管理と負担軽減に向けた議論が深まることが求められます。
Source:
https://news.yahoo.co.jp/articles/dad3b2ccaf2fa3dbe7e80c92f9564e92d16e2401






