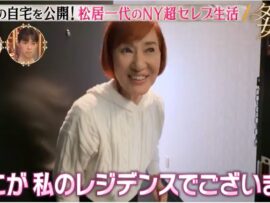普段の生活の中で、夫から毎月振り込まれる生活費を切り詰めて余った分を貯金に回すケースは少なくありません。老後の備えとして貯蓄することは推奨される行動ですが、この「夫から生活費をもらっている」という点が税金面で論点となることがあります。夫婦間のお金のやり取りであっても、受け取り方や使途によっては贈与税の対象となる可能性があるのです。今回の事例、つまり生活費を貯金に回した場合に贈与税として見なされるのかどうか、その税の仕組みを解説します。
贈与税とは?種類を解説
まずは、贈与税の基本的な仕組みについて説明します。贈与税は、個人から現金や不動産などの財産を無償で受け取った際に、その財産に対して課される税金です。年間で一定額を超える財産を受け取った場合、贈与税の申告・納税が必要になります。また、生命保険金を受け取った場合も、契約内容によっては贈与税の対象となることがあります。
贈与税の課税方式には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた財産の合計額にかかる税金です。贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円は「基礎控除額」と呼ばれ、誰から贈与を受けたかに関わらず、受贈者(財産をもらった人)1人につき年間で適用されます。例えば、父から100万円、母から30万円の贈与を同じ年に受けた場合、合計額は130万円となり基礎控除額を超えるため、贈与税の申告が必要になります。一方、父が2人の子どもそれぞれに100万円ずつ贈与した場合、子どもたちはそれぞれ年間110万円以下の贈与となるため、贈与税はかかりません。
相続時精算課税
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫が財産を贈与された場合に選択できる制度です。この制度を選択すると、累計2500万円までの贈与が非課税枠として扱われ、贈与者が亡くなった際に、この非課税枠を超えた贈与分と相続財産を合算して相続税が計算されます。ただし、相続時精算課税を選択した場合も、年間の贈与額から110万円の基礎控除が適用されるようになりました(令和6年1月1日以降の贈与)。例えば、祖父母から2800万円の贈与を受けた孫(18歳以上)が相続時精算課税を選択した場合、年間の基礎控除110万円を差し引いた2690万円が相続時精算課税の対象となり、累計の非課税枠2500万円を超える部分(190万円)に対して贈与税が課税されることになります。
贈与税がかからないケースとは?
すべての財産の受け取りに贈与税がかかるわけではありません。例外として贈与税が非課税となる財産には、以下のようなものが挙げられます。
- 法人からの贈与財産
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、通常の日常生活に必要な生活費や教育費として渡される金銭
- 社会通念上相当と認められる香典や花代、お歳暮、お見舞金などの贈答
- 特定の要件を満たす住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置
- 選挙活動に関して公職選挙法の規定により受けた金銭、物品
- 特定の公益を目的とする事業への寄付
特に重要なのが、夫婦間や親子間での「通常の生活費や教育費」は贈与税の対象とならないという点です。これは、扶養義務の履行として行われる性質のお金だからです。
 夫婦間の生活費を節約し、貯金する手元(贈与税関連のイメージ)
夫婦間の生活費を節約し、貯金する手元(贈与税関連のイメージ)
生活費を「貯金」した場合の注意点
では、今回の事例のように、夫から受け取った生活費を切り詰めて貯金に回した場合、贈与税はかかるのでしょうか。
結論から言うと、生活費として受け取ったお金を貯金したり、株式や不動産などの購入資金に充てたりした場合は、贈与税の対象となる可能性があります。なぜなら、「通常の生活費」として非課税になるのは、あくまで「生活のために使用されたお金」だからです。生活費として受け取ったお金であっても、それが使われずに貯蓄されたり、別の目的(投資など)に使われたりすると、それは生活費としての性質を失い、「贈与」と見なされる可能性があるのです。
過去には、いわゆる「へそくり」が夫の財産と見なされた裁判事例もあります。生活費の残りを妻が個人的に貯めた場合、それは夫から妻への贈与であると判断されるリスクがあります。もし、生活費とは別に、夫が妻に財産を贈与したい意向で貯蓄をしてもらう場合は、後々の誤解や税務署からの指摘を避けるためにも、贈与契約書を作成するなどして、贈与の意思と内容を明確にしておくことが望ましいでしょう。
家族間でもらう生活費は「必要な用途」に使うことが重要
夫婦間であっても、生活費として受け取ったお金を貯金に回すと、贈与税が発生する可能性があります。生活費という名目で受け取った資金は、その名目の通り、日常生活を営むための費用として使うことが税務上のポイントとなります。もらったお金の用途が、当初の目的(生活費)から外れると、贈与と見なされるリスクがあることを理解しておくべきです。
知らず知らずのうちに贈与税の対象となってしまうことを避けるためにも、家族間のお金のやり取りであっても、その性質や税金の仕組みについて正しく理解しておくことが非常に大切です。特に大きな金額の貯蓄や投資に回す場合は、税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
参考資料:
- 金融分野に関する専門家の解説(FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー)
- Source link