レギュラーガソリンの価格が高止まりを続ける中、消費者の負担を軽減すべく「ガソリン暫定税率の廃止」が議論されています。しかし、この減税策がそのまま国民の負担軽減に直結するとは限らない状況が浮上しています。税率廃止によって生じる巨額の財源不足を補うため、政府・与党は新たな税負担の仕組み導入を検討しており、結果として「減税のはずが実質的に増税になるのでは?」という懸念が広がっています。本記事では、ガソリン価格の現状、暫定税率の歴史と課題、そして国民が直面する可能性のある「新たな税負担」について詳しく解説します。
高止まり続くガソリン価格とドライバーの切実な声
経済産業省が発表したレギュラーガソリンの全国平均小売価格は、一時的な値下がりがあったものの、依然として高水準で推移しており、多くのドライバーや運送事業者に重くのしかかっています。都内のガソリンスタンドでは、ドライバーから「今高い。軽油でもガソリンでも変わらない」「トラック会社の運賃も上がってくる、みんなが大変」といった切実な声が聞かれます。
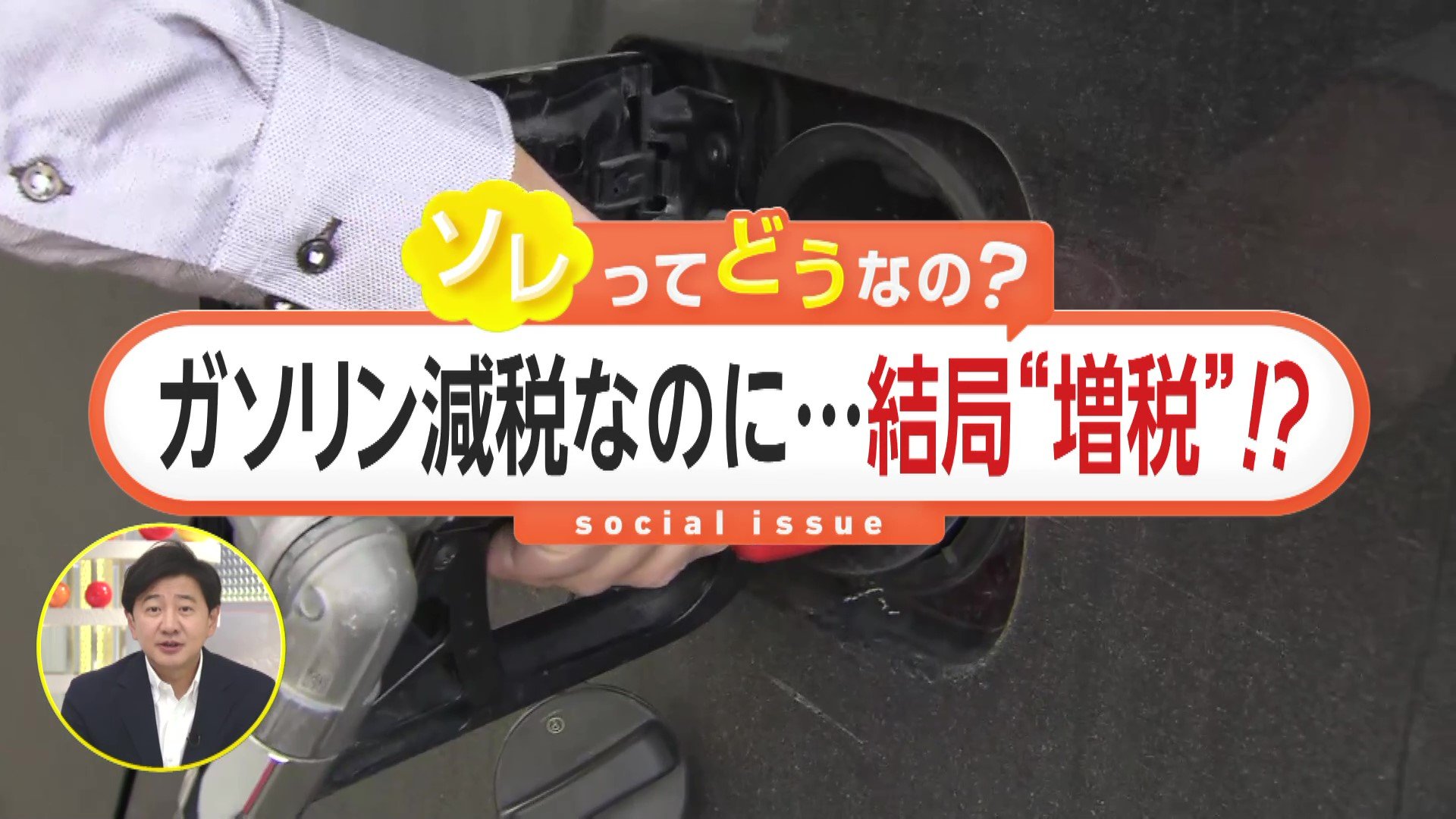 高止まりが続くガソリン価格と街頭で取材に応じるドライバー
高止まりが続くガソリン価格と街頭で取材に応じるドライバー
参議院選挙の結果を受け、与野党はガソリンの暫定税率廃止に向けて動き出していますが、与党側は「恒久的な財源が必要」との姿勢を示しており、ガソリン減税とは別の形での自動車関連税負担導入の可能性が浮上しています。この動きに対し、街のドライバーからは「そんなに車に税金ばかりつけられても困る。(減税の)意味がなくなりますよね」「結局プラスマイナスゼロになる。せっかく暫定税率が廃止になっても、何かで取られたら消費者の負担にかかる」といった不満の声が上がっています。特に「車を利用している人は、車検とか含めて既に税金を取られている。さらにというのは、おかしいというか、きつい」との意見もあり、不公平感も感じられています。
「暫定税率」とは何か?その廃止がもたらす影響
ガソリン暫定税率の歴史と現状
廃止が検討されているガソリンの暫定税率とは、約50年以上前に道路整備の財源不足を補う目的で導入されました。その後、2009年には使途を限定しない一般財源へと変更され、現在に至ります。現行制度では、ガソリン1リットルあたり約25円が暫定税率として課税されており、月に80リットルのガソリンを使用する一般家庭では、年間約2万4000円、月に換算すると2000円程度の追加負担となっています。この負担軽減が、ガソリン減税の主な目的です。
減税の裏にある「財源確保」の課題
ガソリン減税によって暫定税率が廃止された場合、国や地方の財政に大きな穴が開くことが問題視されています。フジテレビの智田裕一解説副委員長は、「ガソリン税の暫定税率が廃止された場合、国や地方の財政に穴が開くので、財源を別のやり方でどう手当てするかが大きな課題になります」と指摘しています。
実際、日本の道路や橋などのインフラは、高度経済成長期に建設されたものが多く、老朽化が深刻な問題となっています。埼玉県八潮市では、下水道管損傷による道路の陥没事故が発生し、復旧作業が現在も続いています。ガソリン減税により、老朽化したインフラの維持や補修に充てられていた約1兆円もの税収が減少すれば、これらの対策が困難になるという懸念があります。この財源を確保するため、減税と引き換えに異なる形での新たな税負担の仕組みが導入される可能性が浮上しているのです。
「看板の掛け替え」に過ぎない新たな税負担への懸念
智田裕一解説副委員長は、この新たな税負担の可能性について、「道路の整備や老朽化対策にたくさんのお金がかかる現状を踏まえて、検討される可能性が出てきているのが、自動車ユーザーに暫定税率分を別の名目で引き続き負担してもらうというやり方です」と説明しています。しかし、これは「看板の掛け替えに過ぎない」として、強い反発を招くことが想定されます。
国民の声が示すように、せっかくのガソリン減税が、別の名目での税負担によって実質的に帳消しになる「プラスマイナスゼロ」の状態になることは、消費者にとって納得のいくものではありません。自動車ユーザーは既に車検費用など多くの税金を負担しており、さらなる追加負担は、経済的な困難を増すばかりか、政策への不信感にもつながりかねません。
ガソリンの暫定税率廃止が、真に国民の負担軽減につながるのか、それとも形を変えた増税となるのか、今後の与野党の議論と政府の具体的な政策決定が注視されます。老朽化するインフラの維持と、国民の生活負担軽減という二つの重要な課題に対し、バランスの取れた解決策が求められています。
参考文献
- FNNプライムオンライン. (2023年8月26日). ガソリン減税のはずが結局増税!? ソレってどうなの? [画像]ガソリンの暫定税率が廃止されるとどうなる?. Yahoo!ニュース. Retrieved from https://news.yahoo.co.jp/articles/f071e5d56eb065b4a86b4be5aebed40df591a131





