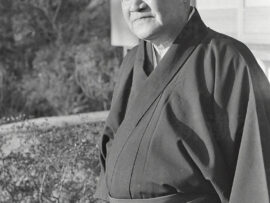VTuber業界は目覚ましい成長を遂げている。VTuberグループ「ホロライブ」を運営するカバー株式会社は売上434億円(前年比+43.9%)、同じく「にじさんじ」を運営するANYCOLOR株式会社も429億円(前年比+34.0%)と、いずれも過去最高の業績を更新した。ホロライブは大阪万博への出演など、世間の注目度も高まっている。しかし、その表面的な好業績の裏側で、静かに警戒すべき兆候が現れ始めている。2025年4月16日、英語圏向けに活動するホロライブEnglish所属の「がうる・ぐら」が卒業を発表すると、カバーの株価はわずか1日で8%下落した。この出来事は、事務所の主力であるIP(キャラクター)が、演者(いわゆる「中の人」)と不可分であることを明確に示し、「人が抜けることは資産が崩れること」という市場の評価を浮き彫りにした。この構造は、ビジネスモデルとして極めて不安定な側面を持っている。かつて絶好調だったYouTuber事務所のUUUMも、演者の人気に過度に依存した構造が崩壊し、退所や独立の連鎖を止められず上場廃止に追い込まれた。現在のVTuber事務所も、これと全く同じ道を歩み始めているように見える。中小企業診断士の視点から、VTuber事務所のビジネスモデルが持つ脆弱性、そして持続可能なVTuber事務所の条件について考察する。
VTuberビジネスモデルの独自性
まず、VTuber事務所の強み、そしてYouTuber事務所との根本的な違いはどこにあるのか。ご存じの通り、VTuberはバーチャルYouTuberの略称であり、2Dや3Dのアバターを介して活動する動画配信者である。演者の姿が直接画面に映ることはなく、アバターそのものの魅力と演者の持つ魅力が融合することで、キャラクターの価値が創造される。この点が、VTuberのビジネスモデルを特徴づける要因となっている。VTuberのビジネスモデルは、広告収益が主体のYouTuberとは異なり、グッズ販売やイベント収益が主要な柱である。演者が直接配信していなくとも、グッズが売れれば収益が生まれる。この点はYouTuber事務所との大きな差異であり、収益基盤の強固さとして評価されてきた。
実際、2025年のカバーの売上において、マーチャンダイジング売上が全体の47.3%(205億円)を占め、ANYCOLORでもコマース部門が65%(278億円)を占めている。物販がビジネスの中心であることは明らかだ。
なぜVTuberはグッズが強いのか
VTuberがグッズ販売にこれほど強い最大の理由は、彼らのキャラクター性が活動開始時点から明確に設計されていることにある。デビューの時点で、プロのイラストレーターによるビジュアルに加え、衣装、髪型、声、性格、話し方、さらには詳細な背景設定などが一体となって設定されており、活動の初期段階からキャラクターとしての人格がファンに提示される。これにより、視聴者はVTuberをアニメやゲームの登場人物のようなキャラクター的存在として、自然に受け入れる構造ができあがっている。
そのため、アクリルスタンド、缶バッジ、ぬいぐるみ、パーカー、キーホルダーといったキャラクターグッズに対して、ファンの心理的な抵抗はほとんどない。むしろ、自分が「推している」対象の公式アイテムを手に入れる行為として、積極的に消費されやすい傾向がある。「推し」を商品として楽しむという日本のオタク文化的な消費スタイルと、VTuberの存在設計が最初から高い親和性を持っているのである。
一方、YouTuberは基本的に「素の人間」として活動しており、実名や顔写真を用いたグッズは、他人の顔を身につけることに対する抵抗感や羞恥心が生じやすい。VTuberは、フィクションとリアルの間に位置する存在として、「人を好きになる感情」と「キャラクターをコレクションする文化」の両方を同時に取り込む設計になっている。この構造こそが、物販が広告収益を凌駕する中核事業となった最大の理由と言える。
「人で稼ぐ」モデルの脆弱性
VTuberのビジネスモデルがグッズ販売やイベントを中心に成功を収めている一方で、その根幹には「人」、すなわち「中の人」である演者の存在が不可欠であるという脆弱性が存在する。キャラクターとしてのIP価値が高いにも関わらず、そのIPは演者のパフォーマンス、個性、ファンとの関係性によって支えられている。
がうる・ぐらの卒業に伴うカバーの株価下落は、市場がこの「演者」と「キャラクター」の不可分性を強く認識していることの証左である。どれほど魅力的なキャラクター設定がなされていても、それを具現化し、ファンとの絆を築くのは「中の人」である演者である。演者が契約を終了し、事務所を離れることは、単に一人の配信者がいなくなるのではなく、その演者が作り上げてきたキャラクターの価値そのものが大きく揺らぐことを意味する。これは、IPの喪失、あるいは大幅な価値低下として捉えられるリスクがある。
この構造は、過去に多くの芸能事務所や、そしてYouTuber事務所が直面してきた課題と共通している。特にUUUMの事例は示唆に富む。UUUMは、トップYouTuberという「人」の人気を基盤に成長したが、人気クリエイターの独立や退所が相次ぎ、その影響力や収益が低下し、最終的には上場廃止に至った。これは、「人で稼ぐ」モデルが抱える、制御困難な属人化リスクが顕在化した典型例と言える。
 VTuber業界の「人で稼ぐ」ビジネスモデルが抱えるリスクを示す図
VTuber業界の「人で稼ぐ」ビジネスモデルが抱えるリスクを示す図
現在のVTuber事務所も、UUUMと同様に、個々の人気VTuberという「人」に収益構造の多くを依存している状態にある。キャラクターとしての側面が強いとはいえ、ファンが応援しているのは、アバターを通して表現される「演者」の人格や魅力が大半である。したがって、特定の人気VTuberが卒業や契約終了といった形で事務所を離れることは、そのVTuberがもたらしていた収益(グッズ、イベント、スパチャ等)だけでなく、事務所全体のブランド価値や将来性に対する市場の信頼をも損なう可能性がある。
この属人化リスクを克服し、持続可能な成長を遂げるためには、VTuber事務所は「人」への依存度を減らし、キャラクターIP自体の価値を高める、あるいは、多様な収益源を確立するなどの戦略が不可欠となる。
出典: Yahoo!ニュース