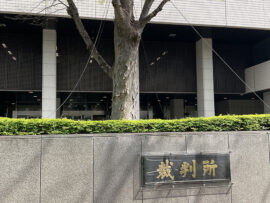「万が一の備え」である生命保険。しかし契約の確認を怠ると、遺族への想いが悲劇に変わることもあります。ここでは、母が遺したはずの死亡保険金を受け取れなかった、45歳の佐藤さん(仮名)の事例を通して、高齢者の生命保険契約に関する確認の重要性を見ていきます。
独り暮らしの母、病と認知の兆候
佐藤恵さん(仮名/45歳)は、夫と子どもがいる会社員です。多忙な日々のなか、離れて暮らす実の母親のことも献身的にサポートしていました。恵さんの母親は夫と早くに別れ、女手一つで恵さんを育て上げました。恵さんが家庭を持ったあとも一人暮らしを続けていましたが、数年前に癌を患い、通院と治療が始まりました。恵さんは仕事や自らの家庭と両立しながら、母親の病院の付き添いや身の回りの世話のため実家を頻繁に訪れていました。
長い間、母は病気と付き合っていましたが、「長く生きてもあなたに迷惑をかけるだけだから」と口にし、手術を望まずにいました。病状はゆっくりと進んでいきました。さらに、周りの人が気づいたときには、認知症の兆候も現れていました。病院で正確に診断されたわけではありませんが、思い出話の途中で会話が途切れたり、同じ内容を何度も話したりすることが目立っていきました。それでも「迷惑をかけてごめんね」と口にしては、2ヵ月に一度の年金(月12万円)が入ると、恵さんにお小遣いを渡してくれるような気遣いもみせていました。
「1,300万円をあなたに」、母からの大切な言葉
ある日のこと、母は恵さんに対し、長らく胸の内に温めていた思いを静かに打ち明けました。「保険に入っているの。私が死んだら、1,300万円が出るようになっているから、手続きをしてね」と、死亡保険金の存在を告げました。この母の言葉は、恵さんにとって、今後の介護費用や生活費の負担を軽減してくれる希望の光のように感じられました。
母の年金は月12万円であり、病状の進行に伴い、入院や治療に関わる費用が増えることへの経済的、精神的なプレッシャーを恵さんは感じていました。母からの保険金の知らせは、こうした負担を乗り越えるための一助となるはずでした。しかし、日々の忙しさに追われるうち、恵さんは母から告げられた生命保険の詳細について、深く確認する機会を得られませんでした。
 生命保険の死亡保険金に関する手続きと契約確認のイメージ画像
生命保険の死亡保険金に関する手続きと契約確認のイメージ画像
突然の別れ、そして保険金を受け取れなかった現実
その後、母親の病状は悪化し入院。「延命治療は望まない」と話していた母は、入院からわずか2週間後、81歳でその生涯を終えました。恵さんは葬儀の手配や遺品整理に追われるなか、ようやく母が話していた生命保険のことを思い出しました。母の遺志を継ぎ、死亡保険金を受け取る手続きを進めようとしましたが、ここで大きな問題に直面します。
母は生前、保険会社の名称や契約番号、正確な保険金額、そして最も重要な「保険証券」や「契約内容がわかる書類」の保管場所について、恵さんに具体的に伝えていませんでした。また、母が認知症の兆候を見せていたため、直接尋ねても明確な答えが得られませんでした。遺品をいくら探しても、生命保険に関する決定的な書類は見つかりません。どの保険会社の契約なのかも不明なままでは、保険金請求の手続きを開始することすら困難でした。結局、母が「最後の願い」として遺したはずの1300万円の死亡保険金は、契約内容や受取人、証券の所在が確認できないため、恵さんが受け取ることは叶いませんでした。
まとめ:高齢者の保険契約、生前の確認が不可欠
佐藤さんの事例は、高齢の親が生命保険に加入していても、その内容や証券の保管場所、受取人指定などが遺族に正確に伝わっていない場合、死亡保険金をスムーズに受け取ることが極めて困難になる現実を示しています。特に、親が認知症を発症していたり、病状が進行したりする前に、家族が契約内容を一緒に確認し、必要な情報を共有しておくことの重要性を浮き彫りにしています。親の「万が一の備え」を無駄にしないためにも、生前にしっかりと話し合い、保険証券や関連書類の場所を把握しておくことが、遺された家族への何よりの配慮となります。
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/cb5fffaba5600b683c471414f34a9236356fb5b1