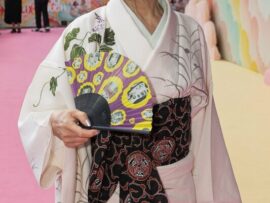日本政府は、半世紀以上続いた実質的な「減反」政策を転換し、コメの「増産」に舵を切る方針を示しました。これは農政における大きな転換点となります。しかし、この政府の新たな方針に対し、現場からは「いまさら増産なんて無理だ」という厳しい声が上がっています。一体、何が問題なのでしょうか。
政府が掲げる「コメ増産」目標
今年4月、政府は中長期的な農政指針である「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定し、コメ政策の大転換を明記しました。具体的には、2023年の生産量791万トンを、2030年には818万トンへ増やすことを目指しています。石破茂首相も7月1日、「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、令和7年産からの増産推進と、不安なく取り組める新政策への転換を表明しました。
高齢化とコストが壁に:農家の現実
しかし、政府が「増産しろ」と言えばすぐにできる、というほど現場は甘くありません。福島県天栄村でコメ農家を営む吉成邦市さんは、「現場を知らない机上の空論だ」と憤ります。増産には作付面積の拡大が不可欠であり、そのためには規模に応じた新たな農業機械が必要となるからです。
さらに、深刻なのが農家の高齢化です。現在、個人経営の米農家の平均年齢は71.1歳(2020年時点)で、70歳以上が58.9%を占めています。こうした状況下で、増産のために高額な投資を行うことは極めて困難だと吉成さんは指摘します。
3000万円の投資負担
吉成さん自身、元村職員で農政担当の経験があり、定年前に脱サラして米農家を始めた際、約2ヘクタールの規模で約3000万円を投資してトラクターや田植え機、コンバインなどを揃えたといいます。退職金だけでは足りず、JAから借り入れも行いました。農業機械の減価償却費だけで、年間約300万円にも上るとのことです。
 日本の米農家と農業機械のイメージ「私が農家になった59歳でも、これだけの投資は覚悟が必要だった。今の66歳では無理でしょう。投資額を回収できるかどうかの不安も大きく、精神的にも続かない」と吉成さんは語ります。経営が成り立つ損益分岐点は、試算では3ヘクタールだったそうです。
日本の米農家と農業機械のイメージ「私が農家になった59歳でも、これだけの投資は覚悟が必要だった。今の66歳では無理でしょう。投資額を回収できるかどうかの不安も大きく、精神的にも続かない」と吉成さんは語ります。経営が成り立つ損益分岐点は、試算では3ヘクタールだったそうです。
このように、政府が掲げるコメ増産目標と、高齢化が進み高額な農業機械への投資が難しい農家の現実との間には、大きな隔たりがあります。半世紀ぶりの農政の大転換は、現場の理解と支援なくしては、絵に描いた餅に終わる可能性も指摘されています。