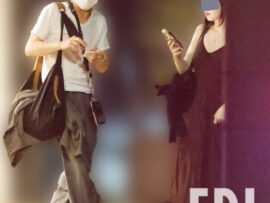トラック運送業界に根深く存在する「多重下請構造」は、中間業者の介在による手数料(ピンハネ)発生が、最終的な実運送を担うドライバーの賃金低下を招く要因として長年問題視されています。相次ぐ規制緩和によりその全体像把握すら困難になっていましたが、物流業界における喫緊の課題である「2024年問題」への対応とも関連し、政府がその是正に向けた検討を進めています。取引の多重化は「物流のワンストップ化による付加価値提供や全体コスト削減」を大義としていますが、その機能が本当に果たされているかは疑問視されています。2025年6月4日に成立した「トラック新法」を受け、国土交通省の「トラック運送業における多重下請構造検討会」がこの問題に関するとりまとめ案を公開し、今後の方向性を示しました。
トラック運送業の「多重下請構造」とは
トラック運送業界で長年の商慣行となっている多重下請構造は、荷主から運送依頼を受けた元請け事業者が、その業務の一部または全部を別の事業者に委託し、さらにその受託者が別の事業者に再委託するという形で、複数の事業者が階層的に連なる構造を指します。この構造において、間に介在する仲介業者が運賃から手数料を差し引く(いわゆる「中抜き」や「ピンハネ」)ため、最終的に実際に運送を行う事業者に支払われる運賃が大幅に目減りしてしまいます。これにより、実運送を担う事業者は利益を確保するためにドライバーの賃金を低く抑えざるを得なくなる状況が生まれています。
 物流を支えるトラック輸送、多重下請構造の問題に関連するイメージ
物流を支えるトラック輸送、多重下請構造の問題に関連するイメージ
「2024年問題」と政府の対応
他の産業と比較して、トラックドライバーは労働時間が約2割長く、収入は約1割低いとされています。有効求人倍率が2倍を超える水準で推移するなど、人手不足も慢性化しています。2024年度から適用された働き方改革関連法および改正改善基準告示により、ドライバーの労働時間に上限が設けられたことで、輸送能力の不足が懸念される「物流の2024年問題」が発生しました。この問題に対応し、物流の担い手を確保するためには、ドライバーに適正な労働条件と賃金を保障するための適正運賃収受の実現が不可欠とされています。政府はこれまでに、「トラック・物流Gメン」による監視体制強化、中小受託取引適正化法(旧下請法)の改正による取引適正化、そして「トラック新法」の成立など、様々な対策を講じてきました。
「多重下請構造検討会」の設置とその実態把握
多重下請構造は、トラック運送業自体が抱える内因的な問題であり、その是正は国や業界団体等の関係者の共通認識となっています。しかし、法規制の対象外である取次事業者などが介在することも多く、その実態の正確な把握は困難でした。荷主や関係者ですら、自身の取引がどの程度多重化しているか、全体像を把握できていないケースも見られました。こうした状況を打破するため、国土交通省は「トラック運送業における多重下請構造検討会」を設置。まずは構造の実態を明らかにするための調査を実施し、その結果に基づいて必要な対策を検討しました。そして、先に成立したトラック新法の内容も踏まえ、今後の多重下請構造の是正に向けた方向性を示す「とりまとめ案」が公開されました。このとりまとめ案は、複雑な構造の解明と是正に向けた政府の具体的な取り組みを示すものとして注目されています。
参照元: Source link