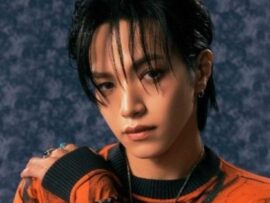戦後、焼け野原となった新宿に活気あふれる闇市を築き上げた男、尾津喜之助。彼は「テキヤの親分」という型破りな立場でありながら、困窮する人々を救うため、無料診療所や無料葬儀社を設立するという一面も持っていた。弱者を助け、強きをくじくという任侠の精神がまだ息づいていた時代、尾津が私財を投じて行った慈善事業には、彼の見栄と本音が複雑に絡み合っていた。本稿は、フリート横田氏の著書『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』の一部に基づき、尾津の無料診療所開設にまつわる知られざる物語とその実情に迫る。
 戦後新宿、焼け野原に立ち並んだ闇市の様子
戦後新宿、焼け野原に立ち並んだ闇市の様子
無料診療所の開設を決意
尾津喜之助には、為政者の思惑を考えている暇などなかった。終戦により困窮の極みにあった新宿の人々に対し、「自分に何ができるか」という一点に熱中していたのである。焼け野原で物を売る闇市だけでなく、さらに踏み込んだ支援を模索していた。安方警察署長から闇市の閉鎖を命じられた頃、尾津は並行して別の事業を進めていたのだ。それは、「カネがなくて医者にかかれない人をタダで診る場所を作ろう」というアイデアだった。一介の露店商親分が、自腹で「無料診療所」を開設するという、まさに大風呂敷と言える計画だった。
名医、ヒゲの長尾さんとの出会い
1945年8月24日、白い長いヒゲをたくわえ、千鳥足で新宿方面へと歩く一人の老人がいた。彼は辻々で「先生!」と声をかけられ、街の人々と立ち話をしては豪快に笑う。彼を知る誰もが彼を慕った。日頃から酒を愛し、道端で寝入ってしまうこともあったが、それが彼の愛嬌でもあった。「ヒゲの長尾さん」と呼ばれ親しまれたその老人は、紛れもない医師だった。角筈1丁目の関東尾津組事務所に到着した彼は、奥で尾津と向き合った。酒好き同士、間に酒瓶を置いて語り合い、結局二升を空けた二人は、その夜尾津邸に泊まり込んだ。尾津は彼に無料診療所の院長就任を要請しており、その快諾を得ての祝杯だったのだ。
焼け跡に生まれた救いの手
翌8月26日の昼、酔いも醒めた長尾さんは、尾津のもとを出発し、焼け残っていたフルーツパーラー高野のビルへと向かった。高野の支配人も、フルーツパーラーの営業再開の見通しが立たない状況を鑑み、焼けビルの1室を診察室として貸し出すことを承諾。医薬品については、伊勢丹横にあった尾津のかかりつけ医である篠田病院が都合してくれることになり、篠田病院の副院長が長尾さんの片腕として通ってくれることになった。尾津組の子分たちがすぐにビル周辺の瓦礫を片付け、診察室を設営した。紅白幕を張り、開院の準備は整えられた。
開院初日の光景とその現実
開院初日。午後1時に受付を開始するや否や、医者にかかることができなかった多くの貧しい人々が次々と診療所を訪れた。この日、午後6時の閉院までに診察を受けた病人は171人にものぼった。もちろん、これらの診察にかかる費用の一切は尾津が負担した。こうして、利益を一切求めない、純粋な慈善事業がスタートした。しかし、尾津が自らに課した任侠の精神を十分に満足させてくれたのは、実はほんの最初だけであったという。多くの患者が訪れた一方で、尾津が抱いた期待とは異なる現実が待ち受けていたことを示唆している。
参考文献
- フリート横田『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』