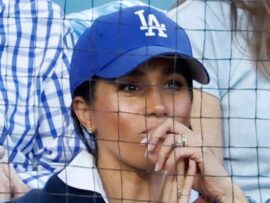日本の農業が抱える高齢化と後継者不足は深刻な問題です。特に、大規模な投資が必要でありながら「儲からない」と評されることの多い米農家では、その実態はより厳しいものがあります。そんな中、東京大学を卒業した米利休氏が、廃業寸前の祖父の米農家を継ぐという異例の決断を下しました。本記事では、米利休氏の著書『東大卒、じいちゃんの田んぼを継ぐ 廃業寸前ギリギリ農家の人生を賭けた挑戦』(KADOKAWA)に基づき、この挑戦が家族にもたらした様々な反応と、日本の農業が直面する現実について深く掘り下げていきます。
 日本の水田と農村風景:後継者問題に直面する米農家のイメージ
日本の水田と農村風景:後継者問題に直面する米農家のイメージ
「農家にならない」からの転換:東大卒・米利休の決断
米利休氏は幼少期から農業に対し良いイメージを持っておらず、「農家にならなくて済むように」と自身の進路を定めてきました。そのため、これまでの人生の選択を180度転換し、「農家を継ぐ」と宣言することは、即断できるほど容易な決断ではありませんでした。それは、これまでの自己を否定し、時にはプライドを捨て去ることに等しい重みを持っていたため、深い葛藤と迷いを伴うものでした。
この一大決心が、家族それぞれに異なる反応を引き起こすことになります。特に、子どもの頃から「勉強を頑張らないと農業しかできない」と刷り込んできた父親の反応は、米利休氏にとって最も意外なものでした。
家族それぞれの葛藤:父、母、そして祖父の思い
米利休氏の農業継承の決断は、家族全員にとって大きな節目となりました。それぞれの立場と過去の経験から、様々な感情が交錯します。
変化した父の認識:中立的な理解者へ
かつて息子に「農業は避けろ」と教えていた父親は、意外にも中立的な立場を示しました。農業法人の社長が家業の経営状況を懸念し、相談に訪れた際、数字に不慣れな祖父に代わって同席したことが転機となります。社長から「やり方次第ではチャンスがある」という話を聞いたことで、父親の農業に対する固定観念が変化したのです。
父親は、大きな収益は期待できなくとも、少なくとも生活に困らない程度の運営は可能であるという感覚を抱くようになりました。自身は農業を継がずに会社員となった経験から、農業の不利な側面をよく理解しているため、息子の決断に対して「本人が望むなら継いでもいいし、継がない気持ちもわかるから何も言わない」という、理解と尊重の姿勢を見せました。
心配する母の愛情:苦労を知るからこその反対
一方、母親は息子の農業継承に反対の立場でした。長年、祖父が農業で苦労する姿を間近で見てきた経験が、その背景にあります。特に、2023年に農業を継続するために借金をせざるを得ない状況に直面した際には、その思いは一層強くなりました。
米利休氏が跡を継ぐか否かを迷っていた時期から、母親は一貫して「儲からない仕事は絶対にやるな」というスタンスを崩しませんでした。これは農業継承そのものへの反対というよりも、愛するわが子が自ら苦労の道を選ぶかもしれない状況を黙って見過ごせない、という親心からくる深い心配の表れでした。
喜びを言葉にした祖父:跡継ぎへの切なる願い
家族の中で最もシンプルかつ感動的な反応を示したのは、祖父でした。米利休氏が農業を継ぐ決意を固めたタイミングで、経営の引き継ぎに関する具体的な話を、父、祖父、そして米利休氏の三人で話し合う機会がありました。この会議に先立ち、両親には既に農業を継ぎたいと伝えていたため、父親から祖父へ「孫(米利休氏)が継ぐと言っているが、どうだ?」と切り出されました。
普段は多くを語らない祖父ですが、この時ばかりは「嬉しい」と、その喜びの気持ちをはっきりと口にしました。祖父のこの言葉は、米利休氏にとって深い感動となり、「必ずこの農家を立て直したい」という強い決意を改めて抱かせた瞬間となりました。
厳しい現実と未来への希望
米利休氏の決断と、それに対する家族の様々な反応は、日本の農業が直面する厳しい現実と、それでもなお未来への希望を求める人々の思いを浮き彫りにしています。若者が「儲からない」と言われる業界に飛び込むことは、個人の勇気だけでなく、日本の食料自給率や地域経済の持続可能性にも深く関わる社会的な挑戦です。米利休氏の物語は、単なる家族の物語に留まらず、日本の農業の現状と、その未来を切り開こうとする若き力の可能性を示唆しています。この挑戦が、日本の農業に新たな光をもたらすことを期待せずにはいられません。
参考文献
- 米利休. (2024). 『東大卒、じいちゃんの田んぼを継ぐ 廃業寸前ギリギリ農家の人生を賭けた挑戦』KADOKAWA.