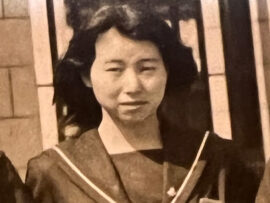近年、日本各地でクマと人間の軋轢が増大し、人身被害は過去最悪のペースで推移しています。政府もこの深刻なクマ被害に対し、クマ対策を急ぐべく閣僚会議を開くなど、本気度をアピールしています。しかし、その対策の最前線である駆除現場では、人間同士のトラブルが頻発し、先行きの危うさが指摘されています。特に北海道積丹町で発生したハンターによる「出動拒否」騒動は、クマ問題の根深い課題を浮き彫りにしています。
 駆除要請拒否が問題となっているクマ被害の象徴としてのツキノワグマ
駆除要請拒否が問題となっているクマ被害の象徴としてのツキノワグマ
異常事態「出動拒否」でヒグマ出没続く町
北海道の日本海側に位置する積丹町では、猟友会が町役場からのヒグマ駆除要請を1カ月以上にわたり拒否し続けるという異例の事態に陥りました。この間、町内では小学校周辺など、人里近い場所へのヒグマの出没が相次いだにもかかわらず、役場は猟友会に駆除を要請できない状況が続いていました。さらに、この出動拒否の事実が議会を通じて町民に説明されていなかったことが発覚。事態を解決しようとしない行政対応に対し、役場には爆破予告が届き、11月1日から予定されていた町主催の文化祭が中止に追い込まれるなど、住民生活にも大きな影響が出ました。
副議長の「暴言」が引き金に:駆除現場の生々しい実態
この騒動の直接的な発端は、9月27日に積丹町議会の海田一時副議長の自宅敷地内でヒグマが捕獲され、その殺処分を巡って現場でトラブルが発生したことでした。現場に駆け付けた9名のハンターに対し、副議長は「こんなに人数いらないだろ」と発言。これに対しハンターの一人が「これからクマを殺処分して箱わなから引っ張り出しますから、一緒にやってみませんか?」と応じると、副議長は激高し、以下のような暴言を繰り返したと現場に立ち会ったハンターは証言しています。
「誰にモノを言っているんだ」「議会の予算を削って辞めさせてやる」「大勢いるのは金がもらえるからだろう」
ハンターによれば、生け捕りにされたヒグマは体重284キロにも及ぶ大物で、少ない人数での処理は極めて困難でした。また、彼らは銃刀法に基づき、周囲に人がおらず跳弾の危険がないなど、安全が確保された環境でなければ発砲できません。副議長が「俺を誰だと思っている」などと大声で叫びながら離れようとしない中、ハンターたちは危険な状況で作業を強いられたといいます。
ボランティアに重くのしかかる負担と誹謗中傷
この副議長は以前から、狩りの現場に現れてはハンターに対し「お前らは下手くそだ」などと誹謗中傷を繰り返してきた存在だったと複数のハンターが証言しています。彼らは長年にわたり不快な思いをしてきたといいます。
そもそも、クマ駆除に従事するハンターは、町からの要請があれば、自身の仕事を中断してボランティアとして出動しています。「会社をクビになると揶揄されるほど忙しない」というのが実情で、特に今年はクマ被害の増加に伴い出動要請が多く、疲弊困憊の状態でした。彼らは町に金銭的な報酬を求めたことはなく、地域住民の安全のために無償で危険な駆除現場に赴いています。
結論
積丹町で発生した「出動拒否」騒動は、深刻化するクマ対策が抱える根深い問題、特に地域社会の安全を守るために命がけで活動するハンターへの敬意と適切な支援の欠如を浮き彫りにしました。行政、住民、そしてハンター間の連携と相互理解がなければ、効果的なクマ対策は実現しません。この問題は、地域社会全体でクマとの共存を探る上で、行政の役割、ハンターの負担、そして住民意識のあり方を改めて問い直すきっかけとなるでしょう。
参考資料
- 「出動拒否騒動まで……」『デイリー新潮』2025年11月5日。
- https://news.yahoo.co.jp/articles/be3570becc599357467bd524d08b95f93cf86cc0