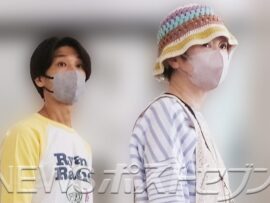家族がいない、頼れる人がいない高齢者にとって、人生の最期を支える「身元保証サービス」は重要な選択肢となりつつあります。しかし、その実態は、預金の無断引き出しや全財産の譲渡を強要する遺言書の作成など、信じがたいトラブルの温床となっているケースが浮上しています。国の規制が不十分なまま野放しになっているNPO法人の運営するサービスの裏側を探ります。
 身寄りのない高齢者が身元保証サービスを利用する様子を示すイメージ写真
身寄りのない高齢者が身元保証サービスを利用する様子を示すイメージ写真
拡大する身元保証サービスの闇と問題点
身元保証サービスは、一般的に病院や介護施設への入所時に必要な保証人としての役割を担い、死後の事務手続きをサポートするものです。身寄りのない高齢者が安心して老後を送るための制度として期待される一方で、その透明性の低さから様々な問題が指摘されています。特に、財産管理に関するトラブルは深刻で、高齢者の大切な資産が不当に流用されるケースが後を絶ちません。
死亡後の預金不正引き出し事例
来院時心肺停止状態――。これは当時85歳だった山根三郎さん(仮名)の死亡診断書に記された一文です。山根さんは妻や子どもがおらず、親しい親族もいなかったため、NPO法人が運営する身元保証サービスと契約し、生前の介護サポートを受けていました。死亡診断書によれば、山根さんは肺炎で某月29日正午に亡くなったとされています。
しかし、関係者から入手した銀行の「ご利用明細」には、山根さんが亡くなった翌月の18日に、何者かによる振り込みの形跡が残されていました。つまり、山根さんの死後約20日後、銀行のキャッシュカードが使用され、ATMから不正な振り込みが行われていたのです。ご利用明細に記載された支店番号から調査したところ、そのATMは山根さんが契約していたNPO法人の事務所近くにあることが判明しました。
死亡した人の預金を銀行から引き出すこと自体は違法ではありませんが、通常は死亡の事実を速やかに銀行に届け出て、口座取引が停止されるのが一般的です。もし親族などが死亡後に現金を引き出した場合でも、死亡時の残高が相続財産となるため、領収書などの保管が義務付けられています。
引き出されたお金の行方と成年後見制度との違い
山根さんの関係者によると、振り込み先は山根さんが以前利用していた訪問介護事業所でした。これは、訪問介護事業所が山根さん宛てに送っていた清算書(請求書)の内容と一致しており、退去時のクリーニング費用10万円、おむつ代約6000円、その他消耗品代などが含まれていました。この事実は、山根さんが生前、NPO法人の「死後事務手続きサービス」と契約していたことを強く示唆しています。
山根さんには「成年後見人」や「保佐人」は付いていませんでした。成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人の財産を管理し、本人に代わって契約締結や医療費の支払いなどを行うことで、悪質な業者から本人を守る役割を果たします。しかし、身元保証サービスは成年後見制度のような法的規制や監督がなく、「野放し」状態にあるのが現状です。この unregulated な状況が、高齢者の財産を巡るトラブルの温床となりやすい大きな要因と言えるでしょう。
まとめ
身寄りのない高齢者のセーフティネットとなるはずの身元保証サービスが、適切に機能しない場合、かえって彼らの財産を危険に晒すことになりかねません。特に、今回の事例に見られるような死後の預金不正引き出しは、サービスの信頼性を根底から揺るがす問題です。高齢者が安心して老後を過ごせる社会を実現するためには、身元保証サービスに対する国の明確な法整備と監督体制の強化が不可欠と言えるでしょう。
参考文献:
- 甚野博則『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(宝島社)
- Yahoo!ニュース / ダイヤモンド・オンライン 掲載記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e3491733ce6b765ea8441bc59319c75b2270a79