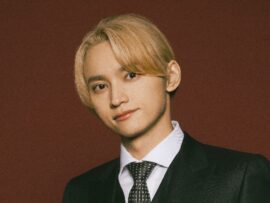世間では、「農家から不当に搾取する存在」「農家を買い叩く悪の組織」といった、農協(JA)に対する根強いイメージが存在します。東京大学を卒業後、実家の米農家を継いだ米利休氏も、かつてはそのような先入観を抱いていた一人でした。しかし、自ら農業現場に立ち、生産から販売までの現実に直面することで、その認識は180度覆されたといいます。同氏の著書から、現代日本の農業における農協の真の姿と、農家が生き残るための鍵について掘り下げていきます。
「農協は悪」という世間のイメージと現実
農業に従事した経験のない方々にとって、農協はとかく農家から利益を搾取している組織、あるいは、農産物を不当に安く買い叩く存在と映りがちです。実際に「農家が買い叩かれている」といった話も耳にすることは珍しくなく、著者自身も少なからずそのイメージを抱いていたと述べています。しかし、もし農協が本当に“悪”であるならば、著者の祖父が長年にわたって農業経営を続けてこられたはずがありません。
農協は全国の地域ごとに存在し、中には一部、農家にとって不利益な運営を行っている組織もあるかもしれません。しかし、少なくとも著者の地元の農協は、農家に対して非常に親切で、その支援に懸命に取り組んでいると強調します。世間一般のイメージとは裏腹に、農協が多くの農家にとって不可欠な存在である現実があるのです。
 日本の豊かな田園風景で作業する農家
日本の豊かな田園風景で作業する農家
なぜ農協が日本の農業に不可欠なのか:その実態とメリット
多くの農家にとって、生産活動は非常に手一杯な状態です。苦労して作物を育てたとしても、その全てを自力で販売できるかというと、それはまた別の困難な課題となります。「作ったはいいが、どうする?」という状況に直面する農家がほとんどです。
ここで農協の最大の強みとなるのが、規格外品を除き、生産された農産物を全量買い取ってくれるという点です。これは農家にとって非常に大きなメリットであり、安定的な販路を確保できるという点で、経営の根幹を支える役割を担っています。農協の卸先である市場の相場に基づいて買取価格が決定され、農協側の販売手数料は5%以下に抑えられています。この低手数料も、農家の手取りを確保する上で重要です。
また、独自に販路を拡大する道を模索する農家もいますが、種子、肥料、農薬といった生産に必要な資材の購入においては、結局のところ農協の世話になることが多いのが実情です。さらに、事業拡大のための資金が必要な際には、農協からの融資を相談するケースも少なくありません。このように、農家は様々な側面で農協に支えられており、農協が存在するからこそ、日本の農業が成り立っている側面があると言えるでしょう。
農家と農協の共存関係:持続可能な農業への鍵
農家と農協は、「もちつもたれつ」の関係、つまり相互に依存し、助け合いながら成り立っています。この共存関係を良好に保ち、うまく付き合っていくことが、現代の日本の農業において農家が生き残っていく上で極めて重要であると米利休氏は指摘します。
農業経営において利益を上げている農家が存在する以上、もし自身が思うように儲かっていないのであれば、それは少なからず自身の経営努力や判断にも原因がある、という姿勢で臨むことが大切だと結んでいます。農協を一方的に「悪」と決めつけるのではなく、その役割とメリットを正しく理解し、積極的に連携していくことが、持続可能な日本の農業を実現するための鍵となるでしょう。