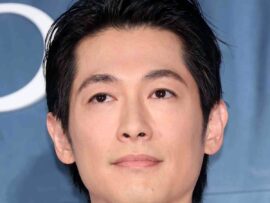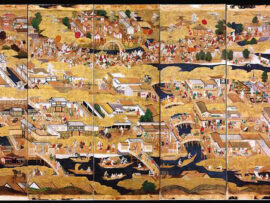近年、日本の都市景観はタワーマンション(タワマン)の林立によって劇的に変化しました。2024年末時点で全国に1561棟ものタワマンが存在すると言われ、それぞれの地域で生活様式、景観、そしてその土地の価値をも大きく変えつつあります。しかし、その足元には、古くからの住民たちの生活圏が今も息づいています。本稿では、垂直に伸びるタワマンとは異なる、水平に広がる「タワマンだけじゃない街」の姿に焦点を当て、日本のタワーマンション開発の原点とされる「与野ハウス」とその周辺地域をレポートします。
日本のタワーマンションの定義と「与野ハウス」の歴史的背景
タワーマンションという言葉に明確な定義はありませんが、一般的には高層の集合住宅を指します。本稿では「2000年以降に竣工した100メートルを超えるマンション」という基準を設けますが、それ以前に建設された歴史的な高層マンションも存在します。その中でも、日本初のタワーマンションとして業界で定説となっているのが、埼玉県さいたま市中央区上落合にある「与野ハウス」です。
 日本初のタワーマンションとされる埼玉県さいたま市中央区の「与野ハウス」の外観
日本初のタワーマンションとされる埼玉県さいたま市中央区の「与野ハウス」の外観
「与野ハウス」は1976年に竣工し、地上21階建てを含む4本の棟で構成されています。当時の広告によると、価格は752万円から3485万円、月額管理費は4500円から1万7100円でした。大卒の初任給が10万円を切る時代において、これは相当な高額であり、当時の日本の住宅事情を鑑みても非常に先進的な集合住宅であったことが伺えます。高さは約60メートルと、現在の超高層マンションと比較すれば控えめですが、当時としては十分に高層建築物と認識されていました。
時を超えて佇む「与野ハウス」と周辺地域の変化
現在、「与野ハウス」を眺めると、その佇まいには現代のタワーマンションのような派手さやブランド感はありません。むしろ、どこか素朴で簡素な印象を受けます。しかし、その外観からは多くの人々の暮らしの気配が濃く感じられ、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。周辺には昔ながらの住宅地や商店が広がり、タワーマンションが林立する現代の都市とは異なる、地域に根ざした生活圏がいまも脈々と続いています。
新宿駅から埼京線で38分という立地にあるこの地域は、大規模な再開発によって大きく変貌を遂げました。タワーマンションの建設を含む都市開発は、確かに街の活性化をもたらす一方で、その土地固有の景観や生活スタイルにも影響を与えます。「与野ハウス」とその周辺を歩くことで、タワーマンションを含む再開発が街をどのように変え、そして何を残してきたのか、その一つの答えを垣間見ることができました。
まとめ
「与野ハウス」は、単に「日本初のタワーマンション」というだけでなく、日本の都市開発と高層集合住宅の歴史における重要なマイルストーンです。その存在は、現代のタワーマンションがもたらす都市の変化と、地域コミュニティが維持しようとする固有の価値との間で、いかにバランスを取るべきかという問いを私たちに投げかけています。これからも、タワーマンションの発展と、その足元に広がる多様な街の姿を注視していくことが重要です。
Source link:
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd1440358da9f857a1fc206201cbf39269a8c389