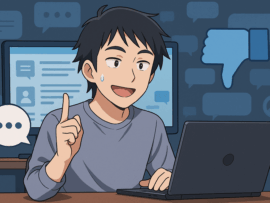2025年7月23日、長らく続いていた日米間の関税交渉がついに合意に至り、これは石破政権にとって重要な外交的成果となりました。交渉の焦点は、自動車製品をはじめとする日本からの輸出品に対する追加関税でした。当初アメリカ側が提示していた24%という高率から、最終的に15%への引き下げが実現し、日本の製造業にとっては大きな恩恵となる見込みです。
日米関税交渉合意:日本の外交的成果とその背景
今回の合意の背景には、日本側がアメリカに対して提示した巨額の対米投資の約束があります。報道によると、日本は今後数年間で総額80兆円(約5500億ドル)規模の対米投資を行うとされています。この投資は、自動車、半導体、インフラ、金融、エネルギーなど多岐にわたる分野に及び、トヨタ、ソニー、ソフトバンクといった日本を代表する大手企業がアメリカ市場での事業拡大を加速させると見られています。
この大規模な投資に対し、ドナルド・トランプ元米大統領は自身のSNS上で「日本が80兆円を投資しても、利益の90%はアメリカが取る」と発言しました。この言葉は一見すると日本側の損失を強調する挑発的なものに聞こえますが、実際には国際投資の構造を理解することで、その真意が見えてきます。
「利益の9割はアメリカが取る」トランプ発言の構造的真意
トランプ氏の発言の意図を具体的に理解するため、仮にトヨタがテキサス州にEV(電気自動車)工場を建設するケースを考えてみましょう。総投資額を1兆円とした場合、その資金の内訳は、工場建設費に5000億円、用地取得に2000億円、設備調達に2000億円、そして残りの1000億円が人件費やインフラ整備に充てられると仮定できます。
工場建設は現地のゼネコンが受注し、資金はアメリカ企業に流れます。用地取得も同様に、アメリカの土地所有者や州政府に支払われます。設備調達の一部には日本企業も関与しますが、多くは現地での調達が中心です。人件費は当然アメリカ人労働者に支払われ、工場が利益を上げれば法人税もアメリカ政府に納められます。
 ドナルド・トランプ元米大統領が会見で発言する様子。日米間の経済交渉における発言に注目が集まる。
ドナルド・トランプ元米大統領が会見で発言する様子。日米間の経済交渉における発言に注目が集まる。
このように、日本企業が巨額の資金を投じても、その大半はアメリカ経済に還元される構造になっているのです。これが「利益の90%をアメリカが取る」というトランプ氏の発言の背景にある構造的な真実です。つまり、「投資によって生まれる経済的恩恵の大部分がアメリカ側に還流する」という現実を端的に表現していると解釈できます。ただし、通常の海外投資でリターンの9割が現地国に集中することは稀であり、今回は特別な「仕掛け」が施されています。
日本の政策金融が支える対米投資:黒子としての役割
今回の対米投資では、日本政府系の金融機関による「政策金融」が重要な役割を果たします。国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)、産業革新投資機構(JIC)、日本政策金融公庫などが、低利・長期の融資やリスク保証を通じて、日本企業の海外展開を強力に支援するのです。
これらの政策金融機関は、民間銀行とは異なり、採算性よりも国策や外交的目標を優先します。利益度外視で資金を供給するため、融資による金利収入や出資による配当といった金融的なリターンをほとんど期待しません。結果として、日本の公的資金がアメリカの雇用創出や設備投資に流れ込み、日本の金融はあたかも「黒子」に徹するかのように機能します。この構造こそが、トランプ氏の「利益の90%」発言の背景にある重要な要素です。日本企業は新たな事業機会を得ますが、金融的な果実はアメリカ側に集中する形となります。これは通常の先進国間投資ではあまり用いられない、政策主導型の経済支援と言えます。
日本側の真の利益:関税引き下げと円安容認の恩恵
では、日本は一方的に損をしているのでしょうか。答えは「否」です。今回の交渉を通じて、日本は自動車関税の引き下げという極めて大きな成果を獲得しました。これに加え、日米間には暗黙の形で「円安容認」という合意があったと見られています。これにより、日本の輸出企業にとっては極めて有利な事業環境が整いました。
トヨタ、マツダ、日産といった国内の主要自動車メーカーは、円安の恩恵を受けて収益を拡大し、株価も上昇基調にあります。特にトヨタは、EV市場における競争力強化のためアメリカ市場への投資を加速させており、今回の合意はその戦略と完全に合致するものです。この対米投資は、単なる経済的支援にとどまらず、日本の主要産業の競争力維持・強化、そして日米同盟の安定化に寄与する戦略的な一手と言えるでしょう。