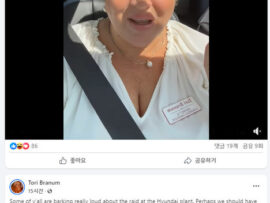コメを田んぼではなく室内で育てる――これまで想像に過ぎなかったこの技術が、現実のものとなろうとしています。兵庫に拠点を置く農業ベンチャー「株式会社あゆち」が、省スペースでコメを高密度栽培できる水耕栽培技術と新品種を開発し、食料安全保障の未来に新たな可能性を提示しました。
「みずのゆめ稲」とは?超矮性・早生型がもたらす革新
水耕栽培は、土を使わず水や液体肥料で植物を育てる画期的な栽培方法です。この技術を稲作に応用することで、天候不順や土壌由来の病害虫の心配がなくなり、コメの安定生産が期待されます。あゆちが育種した新品種「みずのゆめ稲」は、まさにこの水耕栽培のために開発されました。
「みずのゆめ稲」の最大の特徴は、その驚異的な草丈の低さと栽培期間の短さです。通常のイネが90cm~1mに成長するのに対し、「みずのゆめ稲」はわずか15~20cmと、その5分の1程度の超矮性品種です。さらに、収穫までの期間も通常3~4ヵ月かかるところを、この品種は約2ヵ月~2ヵ月半に短縮。これにより、年間最大6回の収穫が可能となり、限られたスペースでの高効率なコメ生産を実現します。
 水耕栽培で育てられる草丈15~20cmの超矮性イネ「みずのゆめ稲」の様子。限られた空間での栽培を可能にするLED照明と栽培槽が特徴。
水耕栽培で育てられる草丈15~20cmの超矮性イネ「みずのゆめ稲」の様子。限られた空間での栽培を可能にするLED照明と栽培槽が特徴。
この超矮性のおかげで、レタスのような背の低い葉物野菜と同様に、多段式での水耕栽培が可能になります。これは、都市部や砂漠、寒冷地など、これまでイネの栽培が困難だった地域でもコメの安定供給を実現する鍵となるでしょう。
安定栽培の鍵:独自技術とLEDシステム
室内でのイネの安定栽培には、湿度、温度、CO2濃度といった厳密な空調管理に加え、適切な光量管理が不可欠です。あゆちでは、独自設計の栽培槽、最適化されたLEDシステム、そして独自の液肥配合を駆使することで、農薬を一切使用せずに安定したコメの育成と収穫を可能にしました。
あゆちの常務取締役である宮崎元氏は、社長の奥眞一氏が大阪府立大学の元教授で農学博士の村瀬治比古氏と2017年頃から試行錯誤を重ねてきた結果、「みずのゆめ稲」が誕生したと説明します。特に、LEDシステムの開発においては、福山総電の大谷典久氏との共同開発が大きな役割を果たしました。
しかし、コメの水耕栽培には課題も残されています。大谷氏は、穀物栽培に必要な光の波長は、レタスの水耕栽培よりも2~3倍の消費電力を要すると指摘します。これにより、現状ではコメの生産コストが高額になってしまう点が課題です。コスト削減の鍵は、限られたメーカーが製造するLEDチップの技術革新が握っており、今後の重要な研究テーマとなっています。
食糧問題解決への展望と今後の課題
あゆちが想定しているのは、貨物コンテナやビニールハウス内での「みずのゆめ稲」の水耕栽培です。さらに将来的には、野菜を育てる「植物工場」のような大規模な「穀物工場」での栽培も視野に入れています。宮崎氏は、「現在、水耕栽培の研究を続けている植物工場は数多くありますが、そうした環境で『みずのゆめ稲』を育てられれば、栽培期間をさらに短縮できるはずです」と、今後の可能性に期待を寄せます。
コスト面の課題や、栽培のさらなる安定化、量産体制の構築など、取り組むべきことは多々あります。しかし、この「みずのゆめ稲」が持つ可能性は計り知れません。あゆちは、この革新的な技術をより多くの人々に知ってもらい、資本力を持つ企業との連携を通じて、「みずのゆめ稲」の潜在能力を最大限に引き出すことを目指しています。食料安全保障への貢献、そして持続可能な農業の未来に向けた大きな一歩となることでしょう。