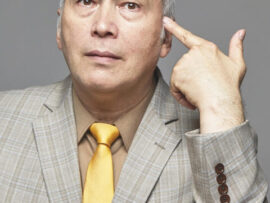近年、スウェーデンやノルウェーなど一部の国で学力低下を背景に教育のアナログ回帰が進むという報道が増え、日本国内でもデジタル化への懸念が指摘されています。しかし、これらの議論には客観的なデータに基づく検証が不可欠です。本稿では、OECD(経済協力開発機構)教育スキル局就学前学校教育課(PISA担当)の小原ベルファリゆり氏へのインタビューを通じ、教育のデジタル化を巡る国際的な動向と、デジタル活用と学力の関連性について深掘りします。
この議論を深める上で、「教育のアナログ回帰は世界的な潮流なのか?」「デジタル化と学力の関連性はデータでどう示されているか?」「日本の教育デジタル化の国際的な評価は?」「今後の世界の教育デジタル化は?」といった問いに対するエビデンスに基づく視点が求められます。OECDは国際的な教育政策に対して中立的な立場から調査を行い、豊富なデータを提供しています。
 読書の媒体と読解力の関連性を示す調査結果のグラフ
読書の媒体と読解力の関連性を示す調査結果のグラフ
「教育のアナログ回帰」は世界的な潮流か?OECDの見解
小原ベルファリゆり氏によると、「教育現場におけるアナログ回帰の議論は、スウェーデンやノルウェーなど一部の国で見られるものの、世界的な主流とは言えません。OECDのデータによれば、多くの国はデジタル化の流れに乗っています」。OECDはICTツールに留まらず、より広範な意味での教育のデジタル化を捉えており、デジタルによる教育機会の拡大と、それに伴うリスク管理のバランスを取る方向へと進んでいます。
OECDはデジタルかアナログかという二元論ではなく、バランスの取れたアプローチを重視しています。現代社会においてデジタルスキルが不可欠である以上、デジタル学習の機会を最大限に活用することは重要です。同時に、学習への悪影響や生徒の健康への負担を避けるため、質の高い教材と学習環境を整備し、リスク管理を徹底することがOECDの基本的な考え方です。
デジタル化と学力の関係、そして教員の役割
教育のデジタル化におけるリスク管理において、最も重要な要素の一つは「教員のデジタルスキル」です。教員がデジタル技術を効果的に指導に活用できるよう、継続的な研修制度の整備が不可欠であると小原氏は強調します。
 デジタル技術を活用し生徒に指導する教員
デジタル技術を活用し生徒に指導する教員
さらに、適切なガイドラインの策定も重要です。地域や学校ごとにデジタル教材などの適切な利用方法を定め、教員に明確な指針を示す必要があります。この際、現場に一方的に押し付けるのではなく、策定プロセスに教員を積極的に参加させ、現場の意見を取り入れることが、実効性のあるガイドライン作りに繋がります。
デジタル技術やAIが教育現場に導入されても、教員の役割は依然として極めて重要です。例えば、ICT端末の学校での学習利用時間が1日7時間以上と過剰な生徒は、数学の成績が他の生徒に比べて低い傾向が見られます。この背景には、デジタル教材に頼りすぎて教員が学習に十分に関与できていないことや、質の低いコンテンツを選んでいること、また過剰なデバイスの利用によって生徒の学習環境が妨げられるなどが考えられます。デジタルに限らず、学習効果を高めるためには、教員が明確な目標意識を持つことが重要です。そのような教員は、デジタル技術が導入されても、目標達成のために最適な学習方法やコンテンツを選定できるでしょう。
結論
「教育のアナログ回帰」は一部の国で議論されているものの、世界的な主流ではありません。OECDのデータが示すように、多くの国は教育のデジタル化を推進しつつ、その潜在的なリスクを適切に管理する「バランスの取れたアプローチ」を目指しています。この中で、教員のデジタルスキル向上、適切なガイドラインの策定、そして何よりも教員が学習目標を明確にし、最適な学習方法を選択する役割が極めて重要であることが浮き彫りになりました。持続可能で質の高い教育を実現するためには、デジタル技術を効果的に活用しつつ、教員と生徒の関係性を中心に据えた総合的な視点が不可欠です。