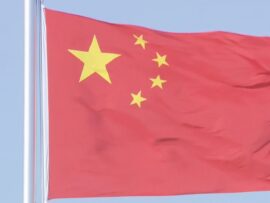昨年発生した「令和のコメ騒動」以来、日本の米価は異常な高値水準で推移し続けている。この状況を打開するための起爆剤として、政府は備蓄米の放出を開始した。特に小泉進次郎氏が農林水産大臣に就任してからは、随意契約による売り渡しや「古古古米」の放出も加わり、店頭では5キロ2000円台の米が久しく見られるようになった。しかし、この「成果」を掲げて政府が臨んだ参院選では自公連立政権が惨敗。物価高には歯止めがかからず、国民の台所は依然として苦しいままだ。地方、特にコメどころに目を向けると、「備蓄米を売っているところなんて見たことがない」という声が、消費者だけでなく業者からも上がっているのが現状である。
 2024年5月末、ドン・キホーテで備蓄米を求めて並ぶ買い物客。コメ不足と消費者の購買意欲を示す光景。
2024年5月末、ドン・キホーテで備蓄米を求めて並ぶ買い物客。コメ不足と消費者の購買意欲を示す光景。
備蓄米放出政策の実態:なぜ小売店と消費者に届かないのか
政府が備蓄米の売り渡し先として中小小売業者に課した条件は、「年間千トン以上1万トン未満」という取り扱い実績である。この基準は、地域に根差した小規模スーパーにとって極めて高いハードルとなる。例えば、新潟市西区でスーパー「いちまん」を経営する高井栄二朗店長は、取材に対し「うちは備蓄米はないですよ。だって(随意契約の)資格がないわけだから」と証言する。高井店長によれば、同店のように年間20〜30トン程度の取り扱い規模では、最初からこの「ゲーム」に参加する資格すら与えられていないという。
「進次郎米」に関するニュースが報じられ始めた頃には、連日多くの消費者から「備蓄米は売っているか」という問い合わせが同店に殺到したというが、やがて同店では取り扱いがないと認知され、問い合わせも落ち着いたという。利益率という点では銘柄米と備蓄米に差はないため、安価な備蓄米を扱えるのであれば、それに越したことはないと小売業者側も考えているにもかかわらず、その恩恵はなかなか地方の小規模店には行き渡らない。
コメどころ新潟の現状:銘柄米の品薄と供給網の危機
世界有数の米どころである新潟県ですら、コメ不足の解消は依然として遠い状況が続いている。高井店長は続ける。「いまでも銘柄米は朝棚に並べると夕方には売り切れ。一家族が購入できるのは一袋と制限していても、毎日売り切れになる」。この状況は、消費者の間に根強い米価高騰への不安と、実際の供給不足が続いていることを示唆している。
さらに深刻なのは、卸売業者側の苦境だ。「問屋も米不足で困っているから、入荷の配達を週3回から週2回、ヘタしたら週1回に減らしてとまで泣きを入れてきますよ」と高井店長は打ち明ける。入荷が週1回になれば、6日間も棚が空の状態に耐えなければならず、新米が出回るまでは「毎日新しい問屋探し」が続くという。「聞けば東京の大手スーパーなんかじゃコメが余っているらしいじゃない。こっちにも売りにきてくれよって感じ。一連の政策を見てきて思うことは、絶対同じこと繰り返して来年もこのままコメ不足が続くと思う。だから知り合いのツテを辿って仕入れの経路開拓をして、農家にも直接アプローチを始めましたよ。新潟県なのにコメ不足ってなんですかね。笑えてきますわ」。米どころでのこの嘆きは、現行政策の機能不全を浮き彫りにしている。
見えない流通の壁:業界内の複雑な関係が供給を妨げる
新潟県内の別の流通業者は、供給の滞りの根深い原因として、複雑な流通問題と業界内の特殊な関係性を指摘する。「結局、卸関係のトップの人たちがみんな知り合いなもんで、『〇〇さんところを優先に卸さなきゃいかんので、本当は備蓄米も卸す余力があるんだけど、ちょっと無理なんですわ』という断られ方をしたこともあります」。これは、大手卸売業者間の「暗黙の了解」や互助関係が、公平な市場競争を妨げ、結果として末端の小売店や消費者への供給を阻害している可能性を示唆している。
さらに、卸売業者が2次、3次、4次と多層につながっており、互いに融通し合うことで、最終的に消費者に米が届かないという不可解な状況が生まれているという。「例えばウチの卸はA社一社だけだったとして、B社にも卸してもらうように頼むとしますよね。そうすると『A社さんが絡んでますね』と断られて、後々になってA社とB社でコメを融通し合っていることがわかるっていうこと。実際はこんなもんなんですよ」。このような複雑で不透明な流通網は、「コメ不足」という物理的な問題だけでなく、構造的な問題が日本の米市場に横たわっていることを示している。
結論
政府による備蓄米放出は、米価高騰とコメ不足という喫緊の課題に対し、期待された効果を発揮しているとは言い難い。特定の規模を持つ小売業者に限定された随意契約の条件や、業界内に深く根付いた複雑な流通網が、政策の実効性を著しく低下させているのが現状だ。小泉進次郎氏が関わった政策も、地方の現場からは「機能不全」との悲鳴が上がっており、新潟のようなコメどころですら銘柄米の確保に苦慮する状況が続いている。
この一連の問題は、単なる供給不足に留まらず、日本の食料安全保障と国民生活に直結する深刻な課題である。物価高が続く中で、国民の台所を圧迫し続ける米価問題は、来年以降も改善が見られない可能性が高い。政府、農林水産省、そして業界全体が、この「見えない壁」を認識し、より透明で効率的な供給体制を構築するための抜本的な改革に早急に取り組むことが求められている。