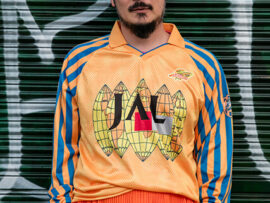敗戦という厳しい結末を知る後世の視点から見れば、無謀な戦争へと突き進んだ当時の日本軍や政府を批判することは容易です。しかし、国全体が「玉砕」へと向かう狂気の中にあっても、悲劇を回避すべく奔走した軍人や官僚が数多く存在した事実を、現代を生きる日本人は忘れてはなりません。本稿では、その一人である陸軍参謀次長・多田駿(ただ はやお)の半生を辿り、彼の知られざる信念と行動に光を当てます。
 陸軍参謀次長・多田駿の肖像写真、日本の歴史的な制服姿
陸軍参謀次長・多田駿の肖像写真、日本の歴史的な制服姿
ポツダム宣言と日中戦争の終結
日本に無条件降伏を求めたポツダム宣言には、米英首脳に加え、中国の蒋介石主席も名を連ねていました。この宣言を1945年8月に受諾したことは、1937年(昭和12年)の盧溝橋事件から始まった「日中戦争(日支事変)」の敗戦をも意味しました。戦史において、陸軍参謀次長であった多田駿の名前が特に大きく取り上げられるのは、開戦から間もない1938年1月15日の「大本営政府連絡会議」でのことです。この会議では、首相、外相、陸海軍の大臣、総長、次長らが集まり、日中事変の今後の戦争方針について議論を交わしました。
大本営政府連絡会議での「戦線不拡大」への訴え
会議の席上、多田駿は蒋介石との和平交渉を打ち切る方向へと傾いていた政府の方針に対し、毅然として反発しました。他の閣僚が「政府不信任ならば内閣総辞職するしかない」と答える中、多田は涙ながらに中国での「戦線不拡大」を強く訴えたと記録されています。
「次長曰く『明治大帝は朕に辞職なしと宣(のたま)えり。国家重大の時期に政府の辞職云々は何ぞや』と声涙(せいるい)共に下る」と、当時の緊迫した状況が伝えられています。この言葉は、国家の危機において政府が責任を放棄しようとすることへの、多田の強い憤りと悲痛なまでの決意を示していました。
 1941年、東條英機陸相と共に歩く陸軍参謀次長・多田駿の姿
1941年、東條英機陸相と共に歩く陸軍参謀次長・多田駿の姿
「支那通」としての多田駿の対中観
多田駿はもともと陸軍内で「支那通」(中国専門家)の軍人として知られ、満洲国軍の育成にも従事していました。1935年8月には、天津の支那駐屯軍司令官に就任。この司令官時代に、多田は現地に暮らす中国人と在留日本人との間に起こりうる衝突を避けるため、「対支基礎的観念」と題する文章をまとめています。この文書には、当時の彼の対中政策に関する独自の視点と、深い洞察が示されていました。
「与うる」主義と共存共栄の提唱
「対支基礎的観念」の中で、多田駿は、中国側に資本や技術、仕事を提供し、「生活の余裕」をもたらすべきだと説いています。これは、単なる支配ではなく、相互利益に基づいた関係構築を目指す彼の思想の表れでした。
「搾取主義を排し『与うる』主義を採るべし 日支経済提携の根本は共存共栄にして、共存共栄の根本は搾取主義を排するに在り。今や疲労困憊瀕死の憐(あわれ)むべき境遇に在る支那民衆を救済するためには、まず『薬』と『栄養』とを与うるの必要あるは当然なり」
多田は、困窮する中国民衆を救済するためには、一方的な搾取ではなく、共存共栄の精神に基づき、積極的に与えることが不可欠であると考えていました。
「職業的親日派」への警鐘と公明正大な態度
しかしその一方で、多田は中国に対する警戒心も忘れていませんでした。特に、自称「親日家」と称し、日本の学校出身で日本語を流暢に話す者たちに対しては、鋭い洞察を示しています。
「職業的親日派を排撃すべし 支那には、日本の学校の出身にして日本語をよくし、金儲けまたは生活の資とせんとする自称親日家の一団あり。[中略]彼らの得意の日本語と日本知識は日本のために計るにあらず、自己のために計るものにして、日本のため必ずしも有利なる存在にあらざるなり」
さらに、多田は不純な権謀術策を用いることへの警鐘も鳴らしていました。
「不純なる権謀術策は王者の態度にあらざるのみならず、斯術(しじゅつ)にかけては結局彼等[中国人]の敵にあらざるなり。[中略]吾人[ごじん・我々]は宜しく公明正大堂々の陣をもって病源を手術すべきなり」
多田は、中国の文化に深く精通し、相手に敬意を払うことを重んじる一方で、権謀術策に長けた中国人に対しては注意を怠りませんでした。これは、彼が多くの現場を経験し、そこで培ったリアリズムに基づいた現実的な認識でした。
結び
陸軍参謀次長・多田駿は、日中戦争の渦中において、国家全体の流れに逆らってまで「戦線不拡大」や共存共栄の思想を訴え続けた稀有な軍人でした。彼の対中観は、深い文化理解と現実的な洞察に裏打ちされており、単なる理想論ではなく、現場の経験から生まれた「リアリズム」に基づいたものでした。戦後の我々が過去を批判する中で、多田駿のように悲劇を回避しようと奔走した人々の存在と、その行動の背後にある信念を改めて見つめ直すことは、現代社会においても重要な意味を持つでしょう。