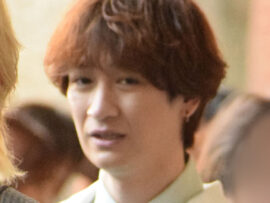「私は日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切り開く責任を担い、この場に立っております」。第104代首相に選出された高市早苗氏の所信表明演説は、保守層からの期待とは裏腹に、予想されたほど保守色が強くない内容でした。政治と選挙に詳しいライターの小川裕夫氏の分析を基に、日本の政界が直面する現状と、高市新政権が抱える課題について深掘りします。
 日本の新首相として会見に臨む高市早苗氏
日本の新首相として会見に臨む高市早苗氏
高市内閣発足の背景と自民党の苦境
2025年10月21日、臨時国会にて高市早苗氏が第104代首相に選出され、新たな内閣が発足しました。高市氏は以前から靖国神社参拝への明確な姿勢を示すなど、筋金入りの保守層から強い支持を集めています。しかし、自由民主党(自民党)全体としては、長年党を支えてきた「岩盤保守層」が、自民党がリベラル寄りに傾倒したと感じたことで離反。これが2024年の衆院選、2025年の参議院選での歴史的な惨敗につながったと分析されています。保守層からは、リベラル化した自民党にようやく保守のリーダーが戻ってきたとの期待が高まっています。
連立解消と政権維持の課題
高市新首相の誕生は喜ばしいニュースである一方、その政権運営には深刻な課題が山積しています。自民党は衆参両院で過半数に達しておらず、さらに26年間続いた公明党との連立政権が、理念や政策の不一致を理由に解消を申し入れられました。これにより、与党の議席はさらに少数となり、安定的な政権維持には他党との協力が不可欠な状況に追い込まれています。この状況は、政権交代への機運を高め、野党が大同団結して国民民主党の玉木雄一郎代表を首班指名する可能性が現実味を帯びるなど、政局は混沌としていました。
野党の動向:維新の閣外協力と「二枚舌」批判
かつては立憲民主党(立憲)、日本維新の会(維新)、国民民主党(国民)の野党3党が連携し、非自民党政権の樹立も視野に入っていましたが、最終的に維新が自民党への閣外協力を決定。これにより、高市内閣の発足が実現しました。この維新の動きに対し、つい先日まで自身を首相とする話し合いを進めていた国民民主党の玉木代表は、維新を「二枚舌」と厳しく批判しました。政治は本来、政策による競争であるべきですが、同時に権力闘争の側面も持ち合わせています。自身の決断力不足を棚に上げて、維新の翻意を非難することは、権力を担う政治家としての自覚が問われると小川氏は指摘します。高市内閣と維新の閣外協力は、一見すると両党の関係強化に見えますが、その実態は逆である可能性も示唆されています。
結論
高市早苗氏の首相就任は、保守層に新たな希望をもたらした一方で、自民党の支持基盤の弱体化、公明党との連立解消、そして野党間の複雑な駆け引きといった多岐にわたる課題を浮き彫りにしました。特に維新の閣外協力は、日本の政治における政党間の力学と権力構造の不安定さを示しています。今後の高市内閣の運営、そして各党の動向が、日本の政治情勢にどのような変化をもたらすのか、その行方が注目されます。