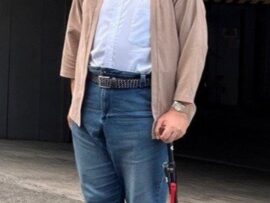米国と日本の間で締結された関税合意に伴い、日本から米国への5500億ドル(約80兆円)の対米投資計画が発表されました。これに対し、ホワイトハウスが公表したファクトシートでは、米国政府やトランプ大統領が主導し、米国産業再生のために日本が資金を供与するかのような印象を与える記述が見られます。特に、投資から得られる利益の9割が米国に帰属するという説明は、日本の対米従属を示唆するもので、大きな波紋を呼んでいます。しかし、このホワイトハウスの発表には、事実との乖離や意図的な情報操作の可能性が指摘されており、その真意を深く掘り下げる必要があります。
5500億ドルの対米投資は民間企業の判断が鍵
ホワイトハウスが示す5500億ドルの対米投資は、あたかも日本政府が約束した確定的な金額であるかのように受け取られがちですが、実態は異なります。この巨額な投資は、日本政府ではなく、日本の民間企業が個々の事業判断に基づいて行うものです。したがって、その実現は企業側の意向に大きく左右されます。トランプ政権が一方的な関税措置を講じるなど、海外企業にとっての米国ビジネスのリスクを高める政策を続ける限り、日本企業は対米投資に対し、これまで以上に慎重な姿勢を取る可能性があります。
この5500億ドルという数字は、日本の民間企業の対米投資を支援するために、国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)といった政府系金融機関が提供し得る、出資・融資・融資保証という3つの手段による支援額の「上限」を意味すると考えられます。決して、日本が米国に直接現金を贈与するものではありません。
「9割の利益は米国に」の真実と問題点
ホワイトハウスのファクトシートで特に不可解なのは、「対米投資から得られる利益の9割が米国に帰属する」という記述です。これについて、赤沢大臣は、政府系金融機関による支援のうち、出資部分(全体のわずか1~2%)に限った話であると説明しています。すなわち、80兆円の総額に対して出資部分は数百億円程度であり、そこから生じる利益も「数百億円の下の方」と述べ、実際のキャッシュフローが米国へ流れるという印象は「的外れで、とんちんかんの極みだ」と強く否定しています。
一方で、赤沢大臣は、当初日本が提案した利益配分が日米で5対5であったものが、トランプ大統領の強い要望により9対1に修正されたことを示唆する発言もしています。この「9対1」という数字が米国に有利であることは認めつつも、「大統領が国内向けに『取った』と言うのはあってしかるべき」という見解を示しています。
政府系金融機関の役割と国益への影響
もし、この発言が国際協力銀行(JBIC)など政府系金融機関が出資したプロジェクトから得られた利益の9割が米国に支払われることを意味するのであれば、これは極めて深刻な問題です。政府系金融機関は、政府の出資によって設立され、日本の国益に資するための公共的な活動を行う組織です。国際協力銀行(JBIC)の目的は、日本企業の海外展開やインフラ事業支援を通じて、日本の国際競争力を強化することにあります。その剰余金は、通常、国庫に納付されるか、政府が管理する特別会計や基金に繰り入れられるべき資金です。
もしこれらの資金が米国政府に支払われるとなれば、それは日本の財政資金を米国政府に贈与する行為に等しく、その分、日本国民の負担が増加することにつながりかねません。これは明らかに日本の国益を損なう事態であり、国際的な合意形成における透明性と公正性の確保が改めて求められます。
まとめ
ホワイトハウスが発表した対米投資に関するファクトシートの記述は、日本側の真意や投資の実態とは異なる部分が多く、特に「5500億ドルは日本からの贈与」「利益の9割が米国へ」といった印象は誤解を招きかねません。実際には、対米投資は日本の民間企業の判断に基づくものであり、政府系金融機関の支援もその上限額を示すものです。利益配分に関する問題は、政府系金融機関の役割と日本の国益に直結する重要な論点であり、透明性のある説明と適切な管理が不可欠です。