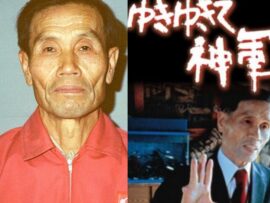7月の参議院選挙で参政党が14議席を獲得し、その躍進は世間の注目を集めました。特に驚きをもって報じられたのは、その支持層の半数近くを女性が占めていたという点です。文筆家の御田寺圭氏は、この現象は偶然ではなく、家庭に入って家事や育児に専念したいと願う女性たちの支持を集めた結果であると分析しています。本稿では、御田寺氏の視点から、参政党がなぜこれほどの女性票を獲得できたのか、その背景にある社会の変化と女性観の変容を深掘りします。
参政党の少子化対策と女性観への議論
参議院選挙での参政党の大躍進後、その熱は冷めつつある一方で、一部のSNSでは参政党の「少子化対策」やそこから垣間見える「女性観」について、いまだに活発な議論が続いています。特に女性たちの間では、これらの政策や見解に対する強い不満や賛否の声が上がっています。しかし、御田寺圭氏は、子どもを産むか産まないかは個人の自由であるという原則は変わらないものの、今後十数年のうちに「産む女性」の社会的尊敬の度合いが急激に高まり、「産まない女性」のそれを大きく上回るフェーズが到来すると予言しています。
 モノクロ写真でインタビューに答える参政党の神谷宗幣代表。参院選での躍進の立役者として、少子化対策など政策に関する自身の見解を述べている様子。
モノクロ写真でインタビューに答える参政党の神谷宗幣代表。参院選での躍進の立役者として、少子化対策など政策に関する自身の見解を述べている様子。
「産む女性」の社会的尊敬が急上昇する未来予測
御田寺氏が指摘するこの「産む女性」の復権は、主に二つの文脈から後押しされるとされます。第一に、日本の出生数はご存じの通り年々激減しており、これは必然的に「社会保障の担い手」の減少を招いています。一人当たりの若い世代が支えなければならない高齢者の数が相対的に増加することで、社会保険料の増大は避けられず、これが若い世代の人生の先行きに暗い影を落とす「重荷」となっているのです。
日本の社会保障を支える「産む女性」の復権
かつては先進的で洗練された「あるべき女性の生き方」として称賛された「あえて産まない」という選択も、そのムードは徐々に変化を見せています。社会保障のリソースやマンパワーが逼迫し、この制度が若い世代の生活や将来に暗い影を落とす実態が広く知れ渡るにつれて、「稼ぎは自己投資や自己利益のために最大限使い切り、年を取ったら産んだ人の子や孫にカネやリソースをタカって悠々自適な老後を送る気満々の人」という眼差しが向けられるようになる、と御田寺氏は見ています。
実際に、このような潮目の変化はすでに生じつつあります。子育て世帯の女性たちを中心に、「なぜ産んだ側の私たちの子どもや孫世代が、産んでいない側の人たちの老後の面倒を見なければならないのか?それは全くフェアではない」という不満の声が持ち上がり始めているのです。
参政党が見出した「不公平感」という鉱脈
この「不公平感」こそが、参政党が気づいたある種の「鉱脈」だったと御田寺氏は分析します。社会の奥底に横たわる、少子化と社会保障を巡る潜在的な不満や葛藤を、参政党は敏感に察知し、それを政策やメッセージに反映させることで、特に家庭や子育てを重視する女性たちの共感を呼び、大量の支持を集めることに成功したのです。
結論
参議院選挙における参政党の躍進、特に女性からの強い支持は、単なる偶然ではなく、日本の抱える少子化問題と社会保障制度の持続可能性に対する社会全体の潜在的な不安と不満が顕在化した結果であると言えるでしょう。文筆家の御田寺圭氏が指摘するように、「産む女性」への社会的尊敬が高まり、「産まない女性」への視線が変わるという潮目の変化は、すでに始まっています。参政党はこの社会の変化の兆しをいち早く捉え、その不公平感を解消しようとするメッセージを発信することで、新たな支持層を獲得する「鉱脈」を発見したのです。この現象は、これからの日本の政治や社会の動向を占う上で、極めて重要な示唆を与えています。
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/40a81177c6499243411cd4d9c7434c9d1e97ca17