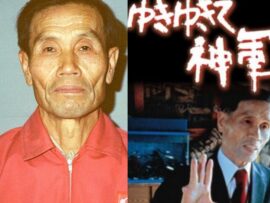1949年(昭和24年)11月3日、日本の科学界に歴史的な瞬間が訪れました。理論物理学者である湯川秀樹氏が、日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞したのです。戦後の混乱と疲弊の中にあった日本にとって、この吉報は国民に大きな希望と誇りをもたらしました。しかし、この偉大な功績の裏には、妻である湯川スミ(澄子)夫人の献身的な支えと、彼女自身の揺るぎない精神がありました。本記事では、当時の「週刊新潮」の記録を紐解き、湯川秀樹博士の偉業と、それを支え、時には彼を導いたスミ夫人の知られざる素顔と「内助の功」に迫ります。
ノーベル賞受賞の舞台裏とスミ夫人の回顧
湯川秀樹氏のノーベル物理学賞受賞は、水泳の古橋廣之進選手が全米水上選手権で世界新記録を樹立した快挙と並び、1949年の日本を熱狂させました。受賞の報を受けた際の様子を、1989年に78歳となっていたスミ夫人は「週刊新潮」の取材に対し、次のように振り返っています。
「10月でしたか、秀樹さんが大学(教授として教鞭をとっていた米コロンビア大学)から帰ってくると“なんだかノーベル賞がもらえるようだよ”と言うのです。彼のところに世界中の報道陣がやってきて、いろいろ取材されたというのです。正式な連絡が来たのはそれから間もなくのことでした」(「週刊新潮」1989年2月2日号より)
秀樹氏の死後も、スミ夫人は夫の遺志を継ぎ、世界連邦の国際運動で世界中を飛び回っていました。この運動は、秀樹氏が1948年(昭和23年)にアルバート・アインシュタイン博士と共に構想を練り始めたものでした。スミ夫人は、「秀樹さんは亡くなる間際まで、人類の幸福を考えていたのです。で、私も、彼が亡くなったあと、海外・国内を問わず、あちこちの会議や講演に出かけています。それは昭和23年、世界連邦の構想ができた時、秀樹さんから“一生懸命やってくれ”と言われたことの続きなのです」と語り、夫への深い敬意と自身の使命感を表明しました。
 1965年11月撮影、ノーベル物理学賞受賞者・湯川秀樹博士とその妻スミ夫人の写真。日本の科学発展を象徴する夫婦像。
1965年11月撮影、ノーベル物理学賞受賞者・湯川秀樹博士とその妻スミ夫人の写真。日本の科学発展を象徴する夫婦像。
哲学者・梅原猛が語るスミ夫人の影響
湯川秀樹氏にとって最大の転機がスミ夫人との結婚だったのではないかと語るのは、哲学者の梅原猛氏です。梅原氏は、秀樹氏の「中間子理論」の研究背景にある厭世観(えんせいかん)を克服しようとする姿勢と、スミ夫人の陽気な性格が絶妙なバランスをもたらしたと分析しています。
「自分の厭世観を克服するために、何か途方もなく大きなことを考えないと、バランスが取れないと研究を続けたのが中間子の理論だったと、湯川先生から聞いたことがあります。一方でスミさんは、無邪気で時に感情が表れやすい活発な方でした。あの奥さんでなければ、先生は隠遁したかもしれない。後のノーベル賞につながる論文も、まだ細かい部分を詰めたいという先生に、すぐに英語で発表してください、と勧めたのは奥さんです。天才でしたが引っ込み思案だった先生の才能を、外に表現する後押しでした」(「週刊新潮」2006年6月1日号「墓碑銘」より)
梅原氏の言葉は、スミ夫人が単なる献身的な妻であるだけでなく、秀樹氏の才能を見抜き、その開花を積極的に促したプロデューサーのような存在であったことを示唆しています。
湯川夫妻の結婚と研究への献身
スミ夫人は1910年(明治43年)に大阪で生まれました。彼女の父である玄洋氏は、現在も続く湯川胃腸病院の初代院長を務めており、夏目漱石の小説『行人』(1912年)にも「毎日午前中に回診する院長」として登場する人物でした。
スミ夫人が3歳年上の秀樹氏と結婚したのは1932年(昭和7年)、彼女が22歳の時でした。結婚2日目には、秀樹氏に学者の妻としての心構えを問い、さらには「ノーベル賞は日本人でも貰えるか」と尋ねたというエピソードは、彼女の先見の明と強い意志を物語っています。
婿養子として湯川家に入った秀樹氏は、スミ夫人の実家からの経済的援助を受けながら、研究に没頭することができました。スミ夫人もまた、夫の研究を最優先に考え、多大な内助の功を発揮しました。戦争を挟みながらも、結婚から17年後、彼らの努力と献身はついに実を結び、湯川秀樹氏のノーベル物理学賞受賞という形で世界に認められることとなりました。
結論
湯川秀樹博士の日本人初のノーベル賞受賞は、単なる個人の栄誉に留まらず、戦後の日本に勇気と希望を与えた歴史的な出来事でした。その偉業の裏には、妻である湯川スミ夫人の揺るぎない愛情と、夫の才能を信じ、時に導く強い精神力がありました。彼女の「内助の功」は、秀樹博士が研究に専念できる環境を作り、彼の偉大な業績へと繋がる道を切り開いたのです。また、秀樹氏の死後も、彼がアインシュタイン博士と共に提唱した世界連邦運動の理想を継承し、国際的な活動に尽力したスミ夫人の姿は、彼女自身の類稀なる人物像を浮き彫りにしています。湯川夫妻の物語は、単なる科学者の伝記ではなく、困難な時代を共に歩み、互いに支え合いながら偉大な遺産を残した夫婦の感動的な記録として、現代に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。
参考文献
- 週刊新潮 1989年2月2日号
- 週刊新潮 2006年6月1日号「墓碑銘」
- Yahoo!ニュース: 「秀樹さんから“一生懸命やってくれ”と」湯川秀樹氏がノーベル賞受賞を語った時、夫人は何を思ったか…(2025年11月3日掲載記事)