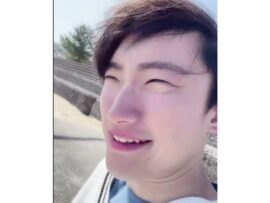本稿では、2010年頃以降の日本における死亡場所の割合変化について国民意識の観点から考察していく。
【写真を見る】自宅死か施設死か「最期をどこで迎える」問題 多死時代を前に病院じゃない「最期の居場所」を探す
希望する「最期の居場所」の国民意識に関する調査は複数存在する。
内閣府の調査では、各年度とも希望する「最期の居場所」を「自宅」と回答した割合が最も高く、「医療施設」「介護施設」を上回っている。
一方で、厚生労働省は具体的なシチュエーションを明示して希望する「最期の居場所」を調査している。
ここでは必ずしも「自宅」が最も高い割合ではなく「医療施設」「介護施設」が最も高い場合もあり、ケースによって構成比に差異が認められる。
両調査の結果を確認すると条件やケースなどによって「結果はさまざま」であった。希望する「最期の居場所」に関する国民意識は2010年頃以降において絶対的なものではなく、状況に左右されながら揺れ動くものだと考えられるだろう。
一方、調査結果が示す希望する「最期の居場所」の割合と実際の死亡場所の構成比には少なからず乖離が認められる。
国民意識が死亡場所の割合変化にどのように影響するのかという視点で考えると、「最期の居場所」に対する国民の「期待度」が死亡場所の割合変化に作用している可能性が指摘できる。
当研究所では「人口減少時代の未来設計図〜社会・経済、そしてマインドの変革〜」をテーマに、人口問題へのリサーチを強化している。
2010年頃以降の日本における死亡場所の割合変化について、特に社会環境変化という観点で、主に介護の視点から考察した。2010年頃以降の日本における死亡場所の割合変化について、特に国民意識の観点から検討する。
なお、人生の最期の迎え方は一人ひとりの意思と尊厳において決定されるべきものである。
レポート内では大局的な死亡場所割合の傾向などを示しているが、決して特定の最期の迎え方を称揚・棄損するような意図はなく、人生の幕の下ろし方に関する多様な価値観・考え方などを進めたり退けたりするような意図もない。